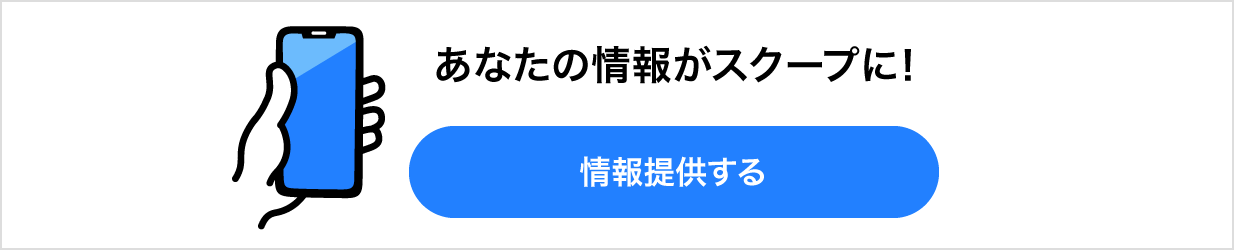数十年前、「2030年の地球」はどう描写されていた?(古市憲寿)
友人が20歳の誕生日を迎えた。2001年生まれである。
かつて「2001年」といえば未来の象徴だった。1968年にアメリカで公開された映画「2001年宇宙の旅」で、人類は月面に入植しているし、木星への有人宇宙探査もしている。
速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…
速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル
速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」
僕が子どもの頃に読んだ図鑑でも、21世紀は希望に溢れていた。『ジュニア サイエンス大図鑑』(学研、1993年)では、飛行機のように宇宙へ行けるスペースプレーンが普及し、夏休みの家族旅行で宇宙ホテルに滞在する様子が描かれていた。
さすがに2001年ではなかったが、それでも2030年の設定である。その頃になれば「ふつうの人でも宇宙へ観光旅行に出かけることができそう」というのだ。そのスペースプレーンを使えば、東京からニューヨークはわずか2時間らしい。
また2030年には、地上千メートルを超えるピラミッド型の「天をつく建造物」、人工的に魚介類を育てる「海洋牧場」、大都市間を結ぶ「地下飛行機」が現実のものになっているという。
もちろん2021年を生きる我々は、そんな「2030年」を信じることはできない。しかしスペースプレーンが当たり前の「2030年」が絶対にあり得なかったかといえば、それも違う。
新型コロナウイルスのワクチンが約1年で実用化できたように、全人類が総力を挙げて宇宙開発に専念していたら、スペースプレーンが日常的な交通手段になっていたかもしれない。少なくとも火星への有人宇宙探査くらいは実現していただろう。高さ千メートルの建造物も技術的に不可能ではない(中東では建設中)。
重要なのは、「技術的に可能なこと」と「社会的に可能なこと」は違うという点だ。コストパフォーマンスを考えると、千メートルのビルなんて必要ないし(最上階までエレベーターで何分かかるの?)、有人宇宙飛行もそれほど需要があるとは思えない(暗いし危ないだけでしょ?)。
歴史は直線的には進まない。ある期間ごとに、それまでのルールが通用しなくなるようなゲームチェンジが起こる。2世紀の倭国大乱の決着には鉄、16世紀の戦国時代終結には鉄砲という新技術が大きな役割を果たした。それが唯一の理由ではないとしても、刀同士で戦っていた時代に鉄砲の威力は計り知れなかった。
1993年刊の『ジュニア サイエンス大図鑑』に決定的に欠けているのは、インターネットが当たり前になる社会という予測だ。「電話回線を使って、パソコンの画面上で情報交換をすることができる」くらいの記述はあるものの、21世紀人がツイッターでくだらない言い争いをしたり、クラブハウスで交わした雑談が週刊誌に暴露されるなんて未来は全く想像していない。
次の30年、40年には何が起こるのだろう。確かなのはゲームチェンジを起こすようなイノベーションの抜けた未来予測は将来、間抜けに見えること。だから「その頃にも猫が人気」など、無難な真理を言っておいたほうが安全なのだろう。