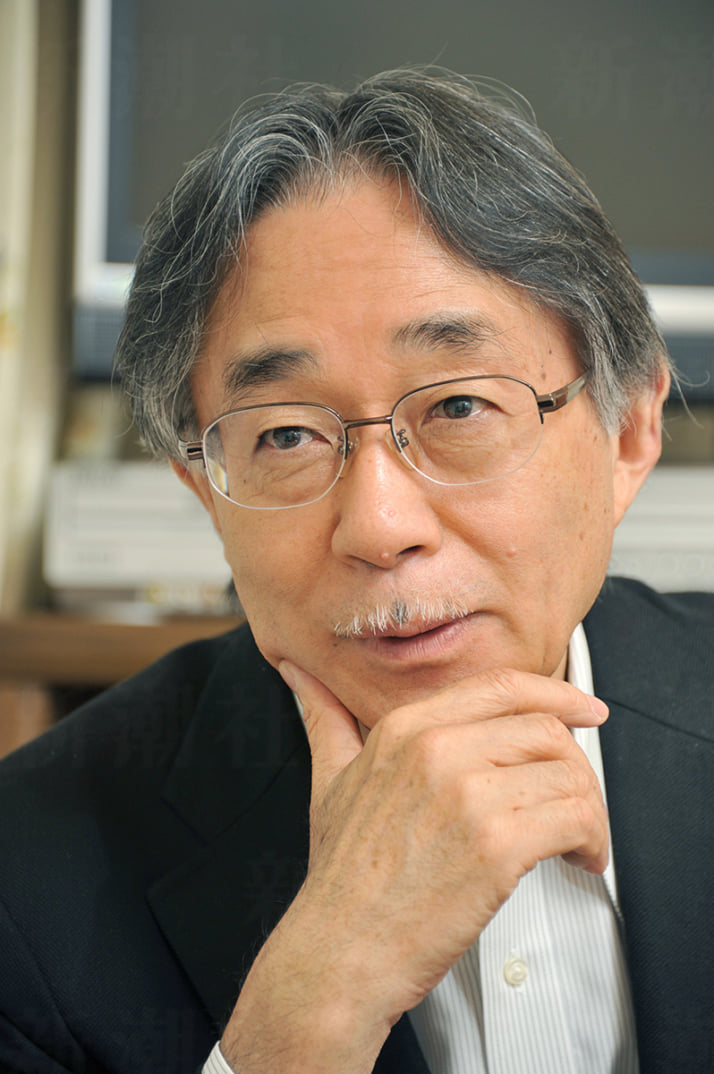「がんになっても日常生活が送れている」 自らもステージ4の医師が実践する「がん共存療法」の確かな可能性 「標準治療の中央値を大きく超える生存期間」の患者も
ステージ4と診断された緩和ケア医の山崎章郎氏が自ら実践している「がん共存療法」。併せて行った臨床試験は3年目を迎えたが、患者の生存期間は標準治療の中央値を超え、QOLも改善されて医療費の抑制にもつながった。その「確かな可能性」をレポートする。
***
2025年5月、連休明けのその日は快晴だった。病院を取り囲む木々の若葉が優しく揺れていた。
外科外来で、自身の体調は良好であり、普段通りの日常を送っていることを伝えつつ、4月末に受けたCT検査の結果を聞いた。
温厚な主治医は「1月のCT検査の結果と変わっていません。安定してますね」と穏やかに説明してくれた。
19年5月、両側肺に多発転移のある、ステージ4の大腸がんが判明してから、6年がたったことになる。3カ月後のCT検査の予約をお願いし、謝辞を伝えて外来を辞した私は、帰り道、この6年間の出来事を振り返っていた。
18年9月、大腸がんが見つかった。11月に受けた手術でステージ3と判明し、5年生存率は70%と告げられた。その生存率を80%に上げるため、再発予防目的の抗がん剤治療が始まった。
間もなく、食欲不振、下痢、手足症候群といった典型的な副作用が出現した。
在宅緩和ケアを実践するため24時間対応の訪問診療に携わっていた私には、仕事の継続が困難と思われるほど辛いものだった。
途中1カ月ほど休薬し、減薬して投与を再開したが、再び副作用は出現した。19年5月、経過確認のCT検査で両側肺の多発転移が判明し、その日からステージ4の大腸がん患者になった。
延命治療に生きる意味を見いだせず……
そして、治癒ではなく、延命目的の、その時点で最善とされる標準治療(抗がん剤治療)が提案された。5年生存率は17%(国立がん研究センター「がん情報サービス」)だった。
抗がん剤の耐え難い副作用を経験してしまった私には、生きがいでもある訪問診療も十分にできない状態での延命治療に意味を見いだすことは難しかった。熟考の末、後はがんの自然経過に委ねようと覚悟し、標準治療を断った。
だが、治療終了後1カ月もすると、副作用も抜けて、仕事も含めいつもの日常が戻ってきた。やがて、本当にこのまま自然経過に委ねていいのだろうか?という思いと共に、脳裏に、私の覚悟に理解を示してくれた大切な人々の、その時の、悲しげで複雑な表情が浮かんできた。
そして、標準治療以外に、日常生活を継続できる副作用の少ない方法があるのであれば、それを見いだし、大切な人々のためにも、精いっぱい生き抜いてみよう。あえて死に急ぐこともないのだ、と考えを改めた。
同時に、自分がステージ4の大腸がん当事者になり、それまで見過ごしてきてしまった標準治療の現実と課題に気付かされた。
それは、治癒を前提にはできず、副作用が避けられない標準治療をどうしても受けたくない患者さんや、標準治療を開始してみたが、副作用で離脱せざるを得なかった患者さんたちの中には、がんの終末期になる前に2度の挫折を経験する方々がいるということだ。
[1/5ページ]