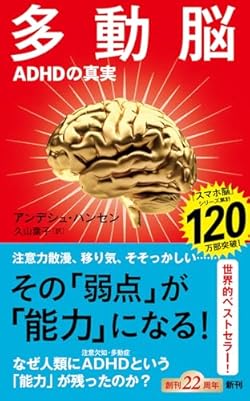「ADHDを引き起こす遺伝子が、人類を繁栄させた」 『スマホ脳』著者が解き明かすADHDの真実
落ち着きがなく指示通りに動けない。社会では困り者扱いされるADHD(注意欠如・多動症)が増えている。世界的ベストセラー『スマホ脳』の著者で精神科医のアンデシュ・ハンセン氏が今回『多動脳』(新潮新書)の翻訳出版にあたり、この“病”の真実に迫る。
***
【写真を見る】『スマホ脳』が世界的ベストセラーとなったアンデシュ・ハンセン氏
そもそもADHDとは何なのかを医師の立場から説明すれば、集中、多動、衝動という三つの分野で問題があるかどうかが診断の基準になります。
集中力を保てない。すぐに気が散る。人の話を聞けない。整理や計画ができない。他にも、頻繁に相手の話を遮ったり、順番が待てなかったりして、じっとしていられず常にスイッチが「オン」の状態になる。絶えず刺激を求め、貧乏揺すりをしたり物をいじったりするなどの特徴もADHDによく見られます。あなたもどれか心当たりがありますか?
無理もありません。誰にでも多少はADHDの傾向があるからです。私もADHDの傾向が強い人間ですが、社会生活で大きな問題が生じなければADHDとは見なされませんし、治療の対象にもなりません。どこまでが「正常」でどこからがADHDか、きっぱりと分かれてはいない。グレーゾーンは非常に広いのです。
「ハイパーフォーカス能力」
ADHDにはポジティブな面もあります。問題点しかなければ、人類の進化の過程でその性質は淘汰されていたでしょう。
ポジティブな面とは、好奇心が旺盛で時にエネルギッシュな実行力を見せることです。また、タブーにとらわれない自由な発想ができ、フレキシブルだったりする。「ハイパーフォーカス能力」と呼ばれるほどの集中力を発揮することもあります。失敗したことにくよくよしないため逆境に強い面もある。
もちろんADHDの人が全員そうだというわけではありませんが、なぜ、こうした両面を持ち合わせているのか。原因は脳の「報酬系」にあるといわれています。
報酬系は快楽中枢などと呼ばれたりもしますが、これは、人の脳にある、自分が好きなこと、例えばおいしいものを食べたり、友達とお喋りしたりする際などに働く神経構造のことです。報酬系では、まず「側坐核」という脳の奥深くにある豆ほどのサイズの部位がドーパミンという神経伝達物質に反応します。
この側坐核は人に心地よさも提供しますが、やろうとすることに「時間をかけたり努力する価値があるか」という判断も伝える。「価値がない」ということになると、「報酬系を活性化してくれる何か他のものを探せ」と指示が出ます。例えば、大抵の学生は授業を聞いているよりスマホを手に取りたくなるし、目の前にいる相手の話がつまらないと「そのネクタイ、ダサいよ」とか別の話題に移したくなる衝動に駆られたりするでしょう。しかし、多くの場合はそうしません。報酬系を活性化させてくれる別のものをすぐに見つけるからです。
[1/5ページ]