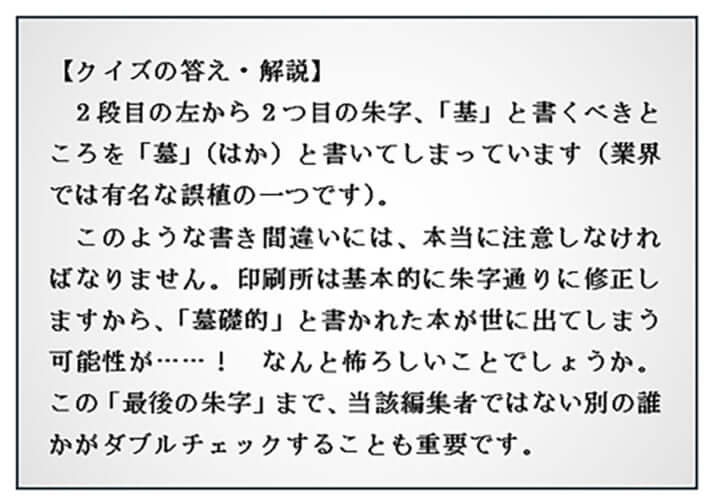「ファクトチェック」や「誤字脱字」だけじゃない…校閲部員が重視する「合わせ」とは何か?
データではなく手書きで修正
ここで、こんな疑問の声が聞こえてきそうです。
「修正って手書きでなくデータで一発、ポンとやればいいんじゃないの?」
結論から言いますと、出版業における修正は、2025年の今でも基本的に手書きベースですし、今後も変わらないでしょう。その理由は、データを丸ごと入れ替えてしまうとむしろ非効率で、かつ事故のもとになるからです(これも重要なテーマなので詳細は改めて)。なお、段落1つ分など部分的なデータの差し替えが行 われることはありますが、その箇所についても「差し替えて終わり」ではなく、新たに調べや素読みをします。
実は、「合わせ」というのは校閲業・出版業にとどまる話ではありません。この連載をお読みくださっている皆様の中にも、wordなどで文章を作成する際、「修正を施した箇所で知らず知らずのうちに文字を1つ多く削ってしまった」「文章を足したことで前後のつながりが変になってしまった」などといったご経験をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。「合わせ」はそのようなミスを撲滅して、よりよい出版物や文章を作っていくために欠かせない作業なのです。
……と、ここまで、校閲の3要素を、世間的には一番の“謎”であろう「合わせ」を中心に紹介しました(ほとんど合わせの話じゃん! というツッコミはナシで……)。そして、次回は3要素それぞれにおける「気を付けるべきポイント」について概観していこうと思います。校閲の話ではありますが、日常で文章を作成する際にも応用できる話ですので是非お付き合いください。
ちなみに、校閲の3要素と書きましたがそれはあくまでゲラ上の話で、他に「スケジュールの交渉」「取引先との折衝」など、ビジネス上のごく一般的な(あまり気が進まない)仕事も日々、行 っていることは念のため付け加えておきます……。