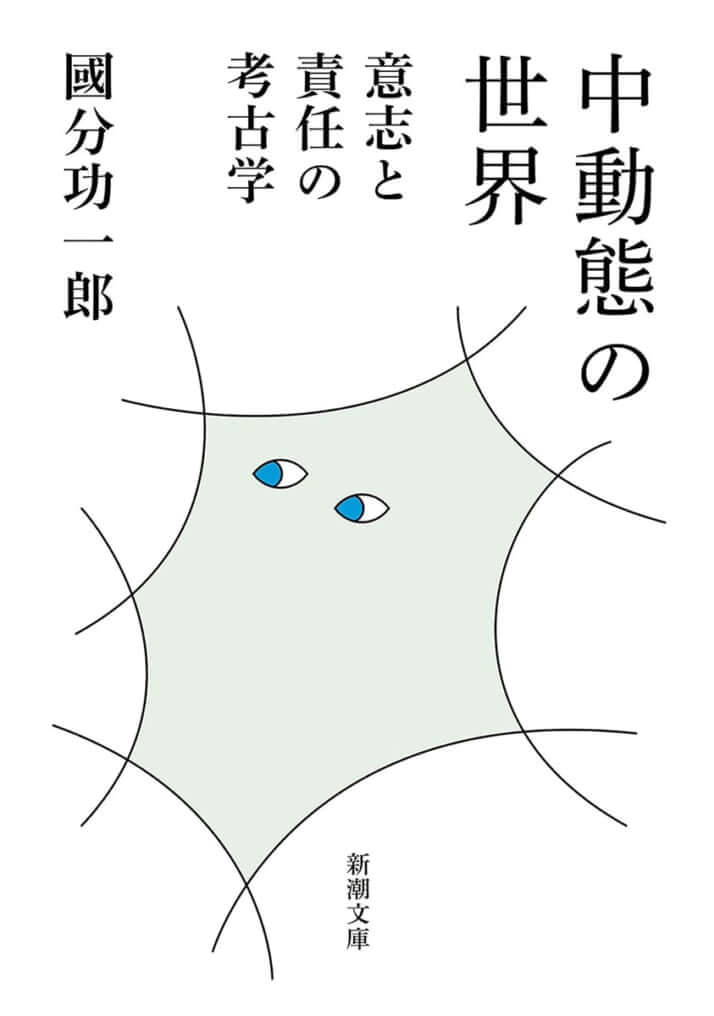「その人がそのままでいられるように」自分ではなく「世界」を変える 名物編集者が語る「ケアと編集」の極意
一般的ではなかったケアという言葉
長大なシリーズとなった「ケアをひらく」のはじまりには、どんなきっかけがあったのだろうか。
「これもやはり、最初に確固たるコンセプトやプランがあったわけではありません。いまから25年ほど前、当時、千葉大学で教えていた広井良典さんとお会いしていて、ケアという考えや行為はすごいものだという話になった。じゃあ広井さんがまずは一冊書いてくださいということで、2000年に『ケア学 越境するケアへ』という本ができました。
広井さんが提示してくださったケアの思想は、膨大な領域にまたがり、つかみどころのなさも感じさせました。この考えを推し進めていくには、シリーズを立ち上げたほうがよさそうだと思い、ケアをテーマに刊行を続けていくことにしました。シリーズをつくってしまったほうが、社内で企画が通りやすいだろうという目論見もありました。
当時ケアという言葉は、『ヘアケア』など美容系の用語として耳にするくらいで、いまほど一般的ではありませんでした。ただ業界的にはケアが注目される事情があったんですね。2000年に介護保険法が施行され、『医学』『看護』に加えて『介護』というジャンルが存在感を増していたのです。そのなかで、ひとつの行為を看護と介護のどちらとみなすかで、小さい対立が起きていました。その解決策として『ケア』を包括概念として使おうという流れが出てきていた。ケアは、注目すべき言葉のひとつだったわけですが、のちにこれほど一般に広まっていくとは、予想もしていませんでした」
シリーズのなかで特に思い出深い本は何か。そう問うと、伊藤亜紗『どもる身体』や、國分功一郎『中動態の世界』を挙げてくれた。
「『どもる身体』は吃音の話です。吃音をどうしたら治るのかではなく、吃音を抱える人は日頃どう対処しているかを明らかにした内容です。たとえば『飛行機』と言いにくい人は、『航空機』と言い換える作業を、話しながらとっさにおこなっています。あらかじめ言い換えの言葉を用意しておくと、それをうまく声にできなくなるので、言い換えは即興であることが求められます。著者の伊藤さんも僕も吃音を持っているので、こうした内容については深い納得感がありました」
[3/4ページ]