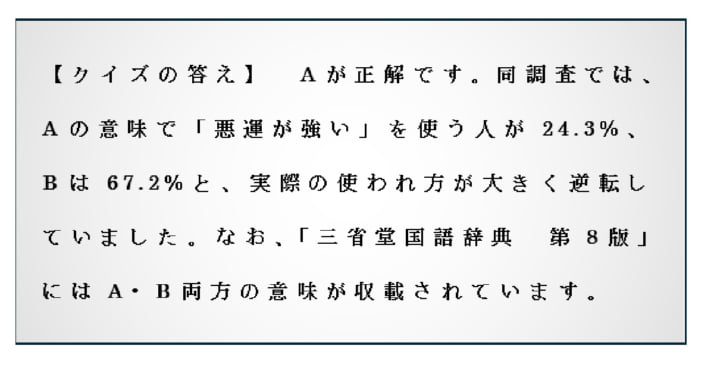校閲の大原則は「原稿を尊重する」だが…「修正すべき点に目をつぶってもいい」わけではない “校閲疑問は多い方がいいのか”問題を考える
校閲の「大原則」とは
話を戻します。では、校閲者は「媒体や原稿によってやり方が変わる」ことを利用(?)して、どんな原稿でも好き放題に、たくさんの疑問を出しても良いものなのでしょうか。
そのことを考えるために、「校閲の大原則」を一つ、皆様にご紹介します。私自身、この仕事に就いた当初、直属の上司(師匠)から次のように言われました。
「原稿通りが一番良い。原稿を尊重して、疑問は最小限に」
つまり、校閲疑問は少なければ少ないほど望ましい、という原則です。
私が最初に配属されたのが文芸誌の「新潮」だったことも大きいとは思うのですが、15年経った今もこの言葉は毎日のように思い出します。
「原稿を尊重する」ということが弊社校閲部のみならず、校閲業全体における大きな指針であることは間違いありません。以前、SNSで話題になった講談社の「校閲十訓」の5番目にも、「原稿重んじとらわれず」と出てきます。
当然、作品は著者のものですから、どんなジャンルであっても、校閲者が思ったことをゲラに全部書いていいわけではありません。また、ゲラを直せば直すほど新たなミスの可能性も増え、印刷所の方や組版担当者の方の負担も増えます。
しかし、ここで重要なポイントがあります。
「原稿の尊重」というのは、「本当は修正すべき要素にもあえて目をつぶっても良い」「確認を怠っても良い」という意味では決してない、ということです。
そして、「たくさん校閲疑問を出してほしい。あとはこちらで考えますので」といったオーダーが編集者や著者から来ることも、実はけっこう多いのです。
さらに、週刊誌校閲の現場では「短くてもわかりやすく、誤解のない記事を作る」というリーダビリティ(読みやすさ)も一段と重要になってくるため、校閲側としてもその一助になる方向で疑問を組み立てていくのが自然です。特にノンフィクション系の文章においては、週刊誌だけでなく書籍や他の雑誌などでも(状況により程度が異なるにしろ)同じことが言えます。
校閲には人間性が表れる
今まで見てきたように、校閲者はすべてのゲラで全く同じ校閲疑問の出し方をすればいい、というものではありません。
また、同じ校閲疑問でも書き方ひとつで印象はガラリと変わります。手書きのやり取りも多いですし、そこには、「人間性」というものが如実に表れるのです(怖ろしいくらいに!)。
やっと結論までたどり着きました。
「校閲疑問は多いほうが良いか、少ないほうが良いか」という質問への回答は、
「校閲疑問は原則として少ないに越したことはないが、時と場合によっては多いほうが良いこともある」
……いやいや、これだけ引き延ばしておいて結論があいまい過ぎだろ、というツッコミは無しでお願いします。校閲って実は、とってもあいまいなところがあるのです。
一つ言えるのは、自分の中にたくさんのバリエーションを持っておいて、どんな状況にも対応できるような校閲者を目指すべきである、ということです。バリエーションを増やすには結局のところ、「経験」しかないように私は思います。
また、出版物を作る仕事というのは、統一されたマニュアルを作りにくいのかもしれません。一冊一冊、作り方が違います。だから、校閲の作業のしかたも一冊一冊違うのです。
しかし、「校閲者によって疑問の出し方が変わってくる」ことにあまり自覚的でない(というか、興味がない?)編集の方がごくまれに見受けられるのも事実です。
いや、実際には誰が校閲するかで色々とかなり変わってくるんですよ、本当に。
……と、こんな偉そうなことを書いている私も、訳書などの経験が少なく、まだまだひよっ子です。ひよっ子で地味な校閲おじさん・甲谷允人は今日も頑張ってゲラを読んでいます。