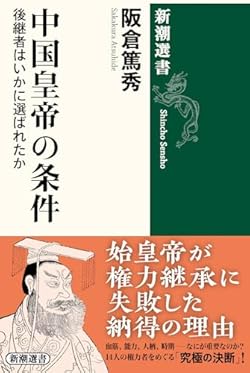「世紀の番狂わせ」で皇帝になった男が味わった「逃亡」と「屈辱」の日々
古今東西、予想外の展開でトップに立つ人物は存在するものだ。現代社会においても、前任者の不祥事による失脚、あるいは企業買収や合併などで、昨日までパッとしなかった社員が、突然社長やリーダーに躍り出る事例は決して少なくない。
歴史を振り返れば、その最たる例として、南宋の初代皇帝、高宗趙構(こうそうちょうこう)が挙げられる。本来、宋王朝の家系において皇位とは縁遠い存在であった彼が、さまざまな偶然が重なり皇帝の座に就く。しかし、実のところ、その治世は北方民族・金軍の侵攻に翻弄される日々だった。
中国史家で関西学院大学名誉教授の阪倉篤秀氏の新刊『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』(新潮選書)に描かれた高宗趙構の生涯は、江南を転々とした末に屈辱的な講和を結びながらも、最終的には宋王朝の維持に成功した苦闘の人生といえる。以下、同書から一部を再編集して紹介する。
***
「臣下の趙構が申します。今、境界を定めるに、淮水(わいすい)の中流を基準としたい。これまでも恩義を受け、私の存在を認めていただいていますが、子孫にも、臣下としての節を守り、皇帝の誕生日と正月元旦には、毎年絶えることなく使者を出してお祝いするようにさせます。
盟約に背くようなことがあれば、天がこれを責めて、我が一族への天命を奪い、国家を倒すことになります。私、ここに誓表を届け、貴国が速やかに誓約書を出されて、我々を安心させてくださるよう願います」
これは中国北部を明け渡し、遍歴ののち、臨安府(りんあんふ)(=杭州〈こうしゅう〉)に拠点を定めて宋朝を継続させた高宗趙構が、1141年に金(きん)の第三代の熙宗完顔亶(きそうわんやんせん)に送った誓書(誓表)である。
これに続いて主戦派の岳飛(がくひ)を更迭して獄に落としたことも報告されて、金宋両国に講和が成立し、「靖康(せいこう)の変(へん)」以後の戦乱状態は収束し、以後20年にわたる平和が到来した。
「紹興和議(しょうこうわぎ)」と呼ぶが、金による趙構の皇帝即位の認定と、金を君主、宋を臣下とする両国の上下関係の規定、淮水流域を基準とする南北の国境画定、そして宋は毎年多額の金品を金に贈る(歳幣〈さいへい〉)取り決めを主要な内容とする。
誰がみても分かる不平等規程で、宋にとっては屈辱そのものであった。ただひとつ趙構個人にとって喜ぶべきは、これをして生母の韋氏(いし)が幽閉先の遼陽(りょうよう・遼東半島の北にある都市)近郊にある五国城(ごこくじょう)から送還されてきたことくらいであろう。
◆「夷をもって夷を制す」
1004年、「せん淵の盟(せんえんのめい)」で宋と遼(りょう)との間で講和が結ばれて平和が維持されたが、この状態に変化が訪れたのは、宋は第八代の徽宗(きそう)、遼は第九代の天祚帝(てんそてい)の時代である。徽宗は第六代神宗(しんそう)の子で、第七代哲宗(てつそう)の弟にあたるが、神宗の政治改革(新法)施行以来の官僚の党派争いが続くなか、およそ政務に興味を示さず、宰相の蔡京(さいけい)と宦官の童貫(どうかん)に頼り切り、遼の天祚帝もよく似た状態で、その統治力は減衰するばかりであった。
このような状勢のなか、遼の北部地域で勢力を蓄えて兵を挙げたのが完顔阿骨打(わんやんあくだ)で、1115年には遼の支配から脱して、皇帝に即位し(太祖)、女真民族の王朝「金」を創建した。これ以後も金の勢いはやむことなく、遼の劣勢を好機とみた宋は、これと連携することによって遼を滅亡に追い込む策略を講じた。いわゆる遼への挟撃作戦「夷(い)をもって夷を制す」で、宋の使者は遼の領域を避けて、山東半島から海路で北上して金に向かい盟約を結んだことから、これを「海上の盟(かいじょうのめい)」と呼ぶ。
南北から攻撃を仕掛けて勝利したのちは、宋は燕雲十六州の領有を復活、遼に払っていた歳幣は金に引継がれることが約された。双方にとって、いや宋にとっては歳幣の支払いは続くとはいえ、なにより念願の燕雲十六州の奪回ができるのであって、極めて望ましい話といえる。
ところがいざ戦闘が始まると、宋は割り当てられていた主要都市での戦闘で敗退を重ねて成果をあげられなかった。かたや金は連戦連勝で予定通りに攻略に成功し、途中で太祖が死亡して弟の完顔呉乞買(わんやんごきつばい)(完顔晟〈せい〉)が即位して跡を継ぎ(太宗)、1125年には遼を滅亡させ、勢いに乗って翌年には開封まで進軍して、これを包囲するに至った。盟約にあった析津府(せきしんふ)と大同府(だいどうふ)の攻略を宋が果たさなかったことに怒った金のしっぺ返しである。
◆人質・趙構
ただここまでの進撃は金にとっては予定外のことで、とても開封を攻略する余力がないことは分かっていた。そのため金は包囲を解いて撤退する条件として、開封城内のありったけの金銀財宝の供出と、宋の皇族を人質として金の軍営へ送致するよう要求した。この1年前に徽宗から皇位を譲られていた長子の欽宗(きんそう)はこれに応じて、城内の金銀をかき集め、さらに徽宗の第9子すなわち弟で康王(こうおう)の称号を持つ(親王〈しんのう〉)趙構を人質とすることを決定した。
ただその裏で、退位していた徽宗は開封を脱出して南方に向かい、欽宗も南方への移動を望みながらも臣下の反対で果たせないままで、この決定に至ったことは知っておくべきであろう。危機に直面しながら、主導者が自分だけ逃げだそうとする、そのような組織に先は望めない。
人質を誰にするかは皇族会議で議論されたが、簡単に決着のつくことではなかった。おそらく長い沈黙が続いたであろうが、そのなか敢然と自ら名乗りをあげたのが趙構であった。金が要求したのは皇族の一員で、なにも徽宗の皇子を要求したわけではないし、もっと低位の皇族でもよさそうなものである。ただ欽宗には誰かを指名する勇気がなく、さらに犠牲になってもいいという皇族がほかに現れなかっただけのことで、ここに当時の王朝中枢部の自己保身に汲々とする様子がみえる。
趙構は皇子とはいえ、武芸にも秀でていたというから、今でいうなら体育会系の気質で、黙ってはいられなかったのかもしれない。彼は出発を控えて、欽宗に「(状勢の変化があり)反転攻勢の好機だと判断する時がおとずれたならば、一人の親王のことなど気にすることはない」と、身を捨てる覚悟を伝えたという。なかなかの「男ぶり」、といいたいところである。
◆「靖康の変」
その後、趙構は思いもかけないことに、随従者の張邦昌(ちょうほうしょう)を残して開封に帰還することを許された。だがここで、趙構は開封には帰らず、進路を逆に東にとり、その間に欽宗から河北兵馬大元帥(かほくへいばだいげんすい)の称号を授けられるとともに、反転攻勢の準備をするようにとの命令を受け、最終的には山東の済州(せいしゅう)まで移動した。
これが命運を分けた。これからすぐに、金は一転して開封への圧迫を強め、欽宗が降伏を表明すると城内に進入して、連れ戻されていた徽宗、そして欽宗、および后妃を含む皇族を一斉に捕縛し、北方の根拠地遼陽に拉致する挙に出たのである。総勢3000人ともいわれ、そのなかに趙構の生母韋氏や妻子も含まれていた。道行の過酷さに、命を落とす人も多かったという。この一連の動きを、時の年号から「靖康の変」と呼ぶ。
◆趙構の南宋皇帝即位
金は全面撤退するに際して、自分たちの影響を残そうとし、張邦昌に楚帝(そてい)の称号を与えて、開封に傀儡(かいらい)政権を樹立させた。張邦昌といえば、金の要求する皇族の送致に随伴して北へ向かうなかで落ち込み、趙構に「これは男としてのこと、めそめそするな」と一喝された人物である。そんな男に傀儡とはいえ政権を担わせることは、どだい無理なことである。案の定、張邦昌は苦境に陥り、哲宗の皇后であった経歴を持つ孟氏(もうし)を開封城中から探し出し、協力を依頼したのである。
ここに孟氏は表舞台に立つことになり、「宋太后(そうたいこう)」(宋王朝の皇太后)と呼ばれて、張邦昌の相談役となった。そこで着目されたのが、河北兵馬大元帥の称号を持って済州に駐留する趙構であった。宋太后は書信で彼に即位を要請したのである。
連行中であった徽宗から、「正式に即位し、父母を救うべきである」との密旨が届いていたことも決め手となり、趙構は開封の東南に位置する応天府(おうてんふ・現在の河南省商丘〈しょうきゅう〉)に移動し、皇帝に即位することになった(高宗)。太祖趙匡胤から数えると10代目、ここまでを北宋、ここからは南宋と呼ぶならば、その初代となる。
宋朝を継いだ限りは、ポーズとしてでも屈辱を晴らす姿勢を示さなければならない。高宗は金との決戦を標榜して主戦派の支持を受けたが、内心はとてもではないが反転攻勢などできないとの思いであった。そのため徐々に主戦派を斥けて講和派を身辺に配置し、戦わずして王朝を維持する方策を探るようになる。
◆「巡幸」という名の「退却」
そこで提議されたのが、東南地方、すなわち江南への巡幸(じゅんこう)である。巡幸とは、皇帝による地方視察をいう。いかに巡幸といいくるめても、形勢不利の危機的状況のなかで皇帝が本拠をあとにするのは、逃避以外のなにものでもない。
しかし反対派の意見を黙殺するなかで、即位2年後にこれは決行された。応天府を出発し、運河を伝って一気に揚州(ようしゅう)まで移動し、ここで駐留して金との講和をはかった。ところが期待外れで、撤退するはずとみていた金は、講和に応じないばかりか、大軍を差し向けてこれを追跡し、あっというまに淮水流域を突破して揚州に迫ってきた。
ここで長江を渡れば騎馬を中心とする金軍は追ってこないだろうと、対岸の鎮江(ちんこう)に移動すると、さすがの金軍もあきらめ北方に撤退する動きをみせた。これを確認した高宗は、当初の目的どおりに、江寧府(こうねいふ)(現在の南京。三国六朝時代の建業〈けんぎょう〉・建康〈けんこう〉)に到達し、ここを行在(あんざい)、すなわち皇帝の臨時的駐在処と定めることにした。
◆逃げて逃げて臨安遷都
高宗はここで再び金に講和を働きかけた。その条件は、趙構は皇帝の称号を用いないこと、さらに即位後に定めた建炎(けんえん)の年号は封印して、金の年号(太宗完顔晟の「天会〈てんかい〉」)を使用するというものであった。
この弱気で安易な希望はかなわなかった。足元をみられたのである。金軍はこれを拒否して南下を続けた。こうなっては皇帝を中心とする集団には警備の兵士はいても、金軍と対抗できる軍隊はなく、ただ逃げるしかない。
ただし、逃げれば追いかけられ、さらに逃げてもさらに追いかけられる状態で、皇帝の集団は蘇州(そしゅう)、そして杭州を越えて越州(えつしゅう)・明州(めいしゅう)と逃げまどい、金軍が迫ると、ついには明州から海辺の定海(ていかい)、さらに対岸の舟山島(しゅうざんとう)に船で渡って一息ついた。
ここでさすがに疲れた金軍が明州から撤退するのを確認すると、また明州に戻ったものの、まだまだ危険とばかりにさらに南に向けて台州(だいしゅう)、そして温州(おんしゅう・浙江省南部)にまでたどり着いた。こうなると金軍もあきらめざるをえなくなった。北方の出身である金の兵士にとっては、当地の高温湿潤気候は耐えきれるものではなく、さらに深入りしすぎて孤立しかねない状態であったからである。
金軍が引きあげるのを確認すると、高宗の一団は踵を返して越州に舞い戻り、いったんはここを紹興府(しょうこうふ)と改名して駐留する計画を立てたが、漕運の便に欠けることから、運河の南端にあたる杭州に移動し、1131年に臨安府と名付けた。応天府から「巡幸」に出発して2年後のことになる。
ただこれで終わりはしなかった。その6年後に、北の五国城に囚われていた徽宗の訃報が届くと、高宗は「仇を討ち、恥をすすぐ」との決意を固めて、江寧府に政権を移動しようとしたが、それも1年であきらめて、結局は臨安府に落ち着くことになった。ここに中国北部は金朝、南部は宋朝という図式が固まり、この3年後に冒頭の誓書が金に届けられたのである。
関連記事【始皇帝はなぜ「人柄がよく、剛毅で武勇と評判の長男」を皇太子に指名しなかったのか?】では、秦の始皇帝の皇位継承の事例から後継者を選ぶ難しさを明らかにする。
また、関連記事【「中国史上最も恐ろしい母親」に口答えできないマザコン皇帝の末路】では、「中国三大悪女」として名前が挙がる「劉邦の正妻」に翻弄された息子(皇帝)の事例を紹介する。
※本記事は、阪倉篤秀著『中国皇帝の条件 後継者はいかに選ばれたか』(新潮選書)の一部を再編集して作成したものです。