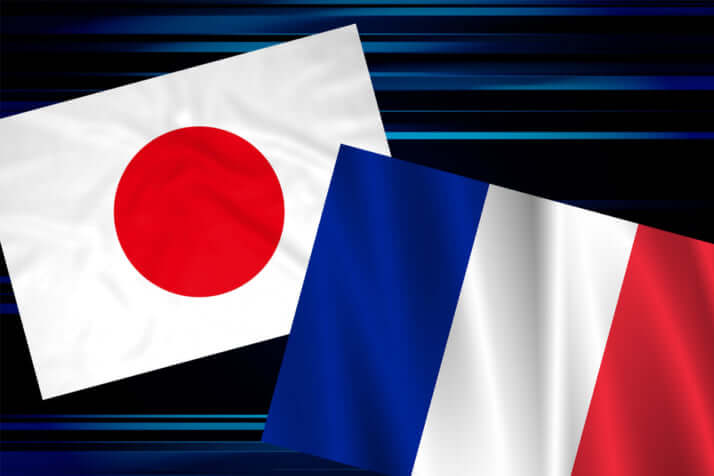「日本語を捨ててフランス語を国語に」 “小説の神様”が唱えた「日本語廃棄論」を言語社会学者が徹底論破
ひとつの文章の中に、漢字、カタカナ、ひらがなという3種類の文字がない混ぜに使用される言語・日本語。しかも、縦書きでも横書きでも表記できて、漢字の読み方は音読みと訓読みの複数あるというのだから、世界中の言語の中でも、その独自性は特筆すべきものである。
速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…
速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル
速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」
もっとも、ほぼ日本でしか使われない日本語は、歴史的には、表音文字だけを使うヨーロッパの言語に比較して「遅れた言語」「文法が不明瞭」「漢字の読みが不統一」と否定的に捉えられることが多かった。
その代表例としてよく話題になるのが、「暗夜行路」「和解」「小僧の神様」「城の崎にて」などの作品で知られる作家・志賀直哉が、終戦直後に総合雑誌「改造」に発表した「国語問題」という論文。「日本語を放棄して、フランス語を国語に採用してはどうか」という大胆な内容だ。
「言葉と文化」の関係について造詣が深い言語社会学者の鈴木孝夫さんは、この志賀の「日本語廃止論」を辛辣に批判している。鈴木さんの著書『閉された言語・日本語の世界【増補新版】』(新潮選書)から、一部を再編集してお届けしよう。
***
日本を文化国にするために
ここで、ある文章を引用したい。
〈 吾々(われわれ)は子供から今の國語(こくご)に慣され、それ程に感じてゐないが、日本の國語程、不完全で不便なものはないと思ふ。その結果、如何に文化の進展が阻害されてゐたかを考へると、これは是非とも此機會(このきかい)に解決しなければならぬ大きな問題である。此事(このこと)なくしては將來(しょうらい)の日本が本統の文化國になれる希望はないと云つても誇張ではない。
日本の國語が如何に不完全であり、不便であるかをここで具體(ぐたい)的に例證(れいしょう)する事は煩(わずら)はし過ぎて私には出來ないが、四十年近い自身の文筆生活で、この事は常に痛感して來た。〉
この文章は1946年に、小説の神様とまで尊敬されていた志賀直哉が、『改造』の4月号に、国語問題として発表した有名な論文の一節である。1946年といえば、第2次世界大戦終了の翌年であり、東京には空襲による焼野原が未だあちこちに残り、食糧不足、インフレ等の社会不安が一時におしよせ、人々は茫然自失の虚脱状態にあった時代である。
戦下の突飛な提案
私は志賀直哉が日本語の問題について、突飛な提案を終戦直後に行ったという話は、実は前からきいていたが、何せ戦後の混乱期のことだし、老作家の一時の錯乱にすぎないものであろうと軽く考えていた。ところが最近図書館で実物を見るに及んで、これは真面目に扱う必要のある、近代の日本人の国語観を典型的に示した重要な論文であることに気がついた。そこでこの雑誌が既に一般の読者の手に入りにくい事情を併せ考え、この論文を少し詳しく取上げてみることにしたのである。
私が志賀のこの論文を真面目に扱う必要があると思う理由は三つある。第一は、ともかく志賀直哉は日本の文学のある面の代表作家であるということ。次に彼の《日本の國語程、不完全で不便なものはない》という考えが、敗戦という未曾有の動乱のさなかにおける一時の思いつきによるものではなく、40年近い彼の文筆生活を通して、常に痛感されていたことだという点。そしてこの文章を書いた頃の志賀は、まだ63歳であるから、高齢のための無責任な放言と笑って済ますことは出来ないというのが第三点である。
「戦争が起きたのは日本語のせい」
さて志賀は前の文に続けて漢字のかな書きとかローマ字書きのような運動が大分昔からあるにもかかわらず、中々成功しないのは、このような国語の部分的改良には致命的な欠陥があるためだとして、一思いに日本語を放棄したらと言う。
〈 私は六十年前、森有禮(ありのり)が英語を國語に採用しようとした事を此戰爭中、度々(たびたび)想起した。若しそれが實現(じつげん)してゐたら、どうであつたらうと考へた。日本の文化が今よりも遙かに進んでゐたであらう事は想像出來る。そして、恐らく今度のやうな戰爭は起つてゐなかつたらうと思つた。吾々の學業も、もつと樂に進んでゐたらうし、學校生活も樂しいものに憶(おも)ひ返す事が出來たらうと、そんな事まで思つた。
吾々は尺貫法を知らない子供逹のやうに、古い國語を知らず、外國語の意識なしに英語を話し、英文を書いてゐたらう。英語辭書(じしょ)にない日本獨特(どくとく)の言葉も澤山(たくさん)出來てゐたらうし、萬葉集や源氏物語も今より遙かに多くの人々に讀(よ)まれてゐたらうといふやうな事までが考へられる。(中略)〉
フランス語国語論
更に志賀は今までの国語を残して悪い所だけを変えて行く改革には賛成できないと主張する。不徹底なものしか出来ないというのがその理由である。
〈 そこで私は此際(このさい)、日本は思ひ切つて世界中で一番いい言語、一番美しい言語をとつて、その儘(まま)、國語に採用してはどうかと考へてゐる。それにはフランス語が最もいいのではないかと思ふ。(中略)不徹底な改革よりもこれは間違ひのない事である。
(中略)
外國語に不案内な私は、フランス語採用を自信を以つていふ程、具體的に分つてゐるわけではないが、フランス語を想つたのは、フランスは文化の進んだ國であり、小説を讀んで見ても何か日本人と通ずるものがあると思はれるし、フランスの詩には和歌俳句等の境地と共通するものがあるとも云はれてゐるし、文人逹によつて或る時、整理された言葉だともいふし、さういふ意味でフランス語が一番よささうな氣がするのである。
私は森有禮の英語採用説から、この事を想ひ、中途半端な改革で、何年何十年の間、片輪な國語で間誤(まご)つくよりはこの方が確實(かくじつ)であり、徹底的であり、賢明であると思ふのである。
國語の切換へに就いて、技術的な面の事は私にはよく分らないが、それ程困難はないと思つてゐる。教員の養成が出來た時に小學一年から、それに切換へればいいと思ふ。(以下略)〉
《日本語不完全論》の典型
私は志賀のこの随筆風の論文を読んで、これまで幾度となく、いろいろな人、それも著名な人によって唱えられてきた《日本語不完全論》の一つの典型をここに見た気持がした。
私の考えでは、この論文には二つの重要な問題が含まれている。
第一は志賀が母国語、ひいては言語というものが、それを使う人にとって、どんな意味があり、どのような深いつながりを持っているものかについて全く無知無感覚であるということ。
第二は、志賀が自分の考えを、どのような表現方法(文章)で示しているかである。
説明の都合上、第二の問題から見ていくことにしたい。
まず彼の言う英語を国語とすれば、日本の文化が進み、従って戦争も起きなかったろうという主張は、論理的に見てもおかしい。英語を使う国が過去に於(おい)てどれだけ戦争をしたか、また文化の高い国がいつも戦争を避けたわけではないことなど、子供にでも分る事実である。しかしこの点は当時の敗戦のショックがひどかったことを考えれば、止むを得ない考え方だと見のがすこともできよう。
『万葉集』や『源氏物語』を英語で?
だが私がどうしても見逃すことが出来ないことは、60年前に初代文部大臣森有礼の提案に従って英語を国語として採用しておいたならば、『万葉集』や、『源氏物語』も、今より遥かに多くの人々に読まれていたろうという真に不可解な議論の進め方である。
もし英語を母国語として日本人が育っていれば、万葉や源氏が今よりは読まれなくなっていたろうが、国を興し文化を発展させるためには、それも止むを得ないとでも言うのなら、少なくとも話の筋道は通るのだが、古い国語が知られなくなるために、今よりはるかに多くの人々が、これらの古典を読むようになるだろうというのは、どう考えても意味がとれない文章である。
非論理的なのは志賀のほう
この例が示すように彼の議論は、論理的な脈絡を無視し、話は必然性のない方向に発展して行く。議論の筋道を追うためには、読者が自由奔放に勝手な想像をめぐらすほか仕方がない。
また話の途中には「……と思われる」「と云われている」などの表現が各所に用いられて意見の主体がぼかされている。その上、自分はよくは知らないがと言っておきながら、その知らないはずのフランス語が、世界で一番美しいすぐれた言語であるらしいという想像または伝聞に基づいて、今度は急転直下、日本国家の百年千年後にまで悔いが残らないために、この際思いきって日本語を放棄してフランス語にしろという重大な結論が、非常に断定的に示されているのである。
私の考えでは、もし言葉を使う人自身にこのような発想や議論の運び方をおかしいと思う感覚がなければ、それはどの言語を国語に採用してみても、明確で力強い、そして美しい文章は書ける筈がない。志賀の場合で言えば、彼の言う日本語の不完全さ不便さとは、彼自身の、文章というものに対する基本的な態度が問題なので、日本語という言語の欠陥とは無関係と言わねばならない。
※鈴木孝夫『閉された言語・日本語の世界【増補新版】』(新潮選書)から一部を再編集。