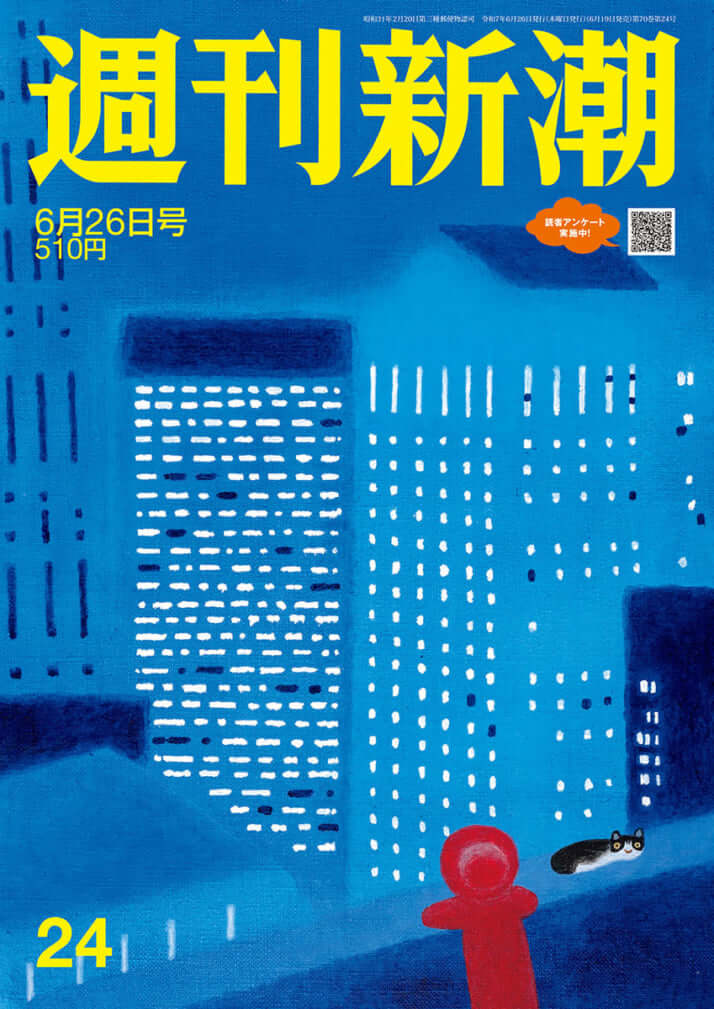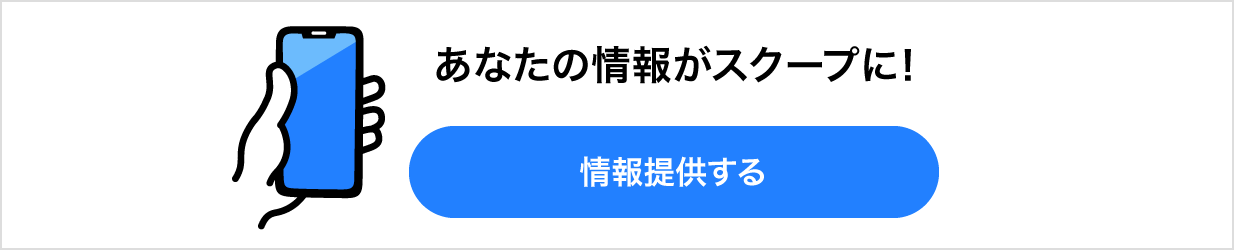「日本本土をいつでも空襲できる状態になりかねない」と識者が警告 自衛隊機に“45m急接近”した中国軍のたくらみとは
日米の「防空の穴」が露見
実際、今回の空母への対応で日米の「防空の穴」が露見してしまったと伊藤氏は語る。
「空母が活動した海域は日本本土とグアムの中間であり、どちらから戦闘機を緊急発進させても1~2時間かかってしまう。最も近いのは硫黄島ですが、滑走路だけで戦闘機や対空ミサイルは配備されていません。今回P-3Cへの急接近に日米は対応できておらず、中国軍は第2列島線付近で自由に活動できると自信を深めたとみていい」
一方、先の織田氏は空母の構造に着目すると「まだまだ見かけ倒し」だとする。
「山東と遼寧はどちらもへさきが反り上がった“スキージャンプ型”です。艦載機は自力で飛び立つ必要があるため、重量がある空中早期警戒機などは発進できません。これが弱点で、遠方の敵機を発見する早期警戒機が運用できなくては、簡単に敵の攻撃を許してしまうのです」
「日本本土にいつでも空襲できる状態になりかねない」
これでは太平洋上で米軍を相手取るなど遠い夢だが、目下試験中の3隻目の空母「福建」が就役すれば話が変わってくるという。
「福建は航空機を機械の力で押し出す“カタパルト型”です。これがあれば空中早期警戒機を挙げて山東・遼寧を支援できるほか、武器弾薬をフル搭載した戦闘機も発進可能です。福建は米国でもまだ完全には実用化できていない、リニアモーターカーの原理を活用した“電磁カタパルト”を搭載する予定です。どこまで実現可能か分かりませんが、テストは進んでいるといいます」(織田氏)
さらに中国は4隻目として、原子力空母を建造しているとの見方もある。先の伊藤教授が先行きを憂える。
「中国は現在、計5隻の空母を配備することを目指しています。もし実現すれば日本の南太平洋上に中国空母が常駐し、日本本土をいつでも空襲できる状態になりかねません。日本も『いずも』や『かが』を改修して空母化しましたが、載せられる戦闘機の数は10機ほどと、山東・遼寧の二十数機に大きく劣ります。台湾有事や中国の海洋進出を考えれば、西太平洋の“穴”を埋めることは急務であり、海空自衛隊の体制強化は必須です」
これが中国の空母進出における“軍事的”な側面であるとすれば、もちろんその裏には“政治的側面”も存在する。習近平国家主席(72)が訓練をどうしても急ぎ実施したかった事情や、飛来する中国機に日本が取り得る対応については、6月19日発売の「週刊新潮」で詳報する。