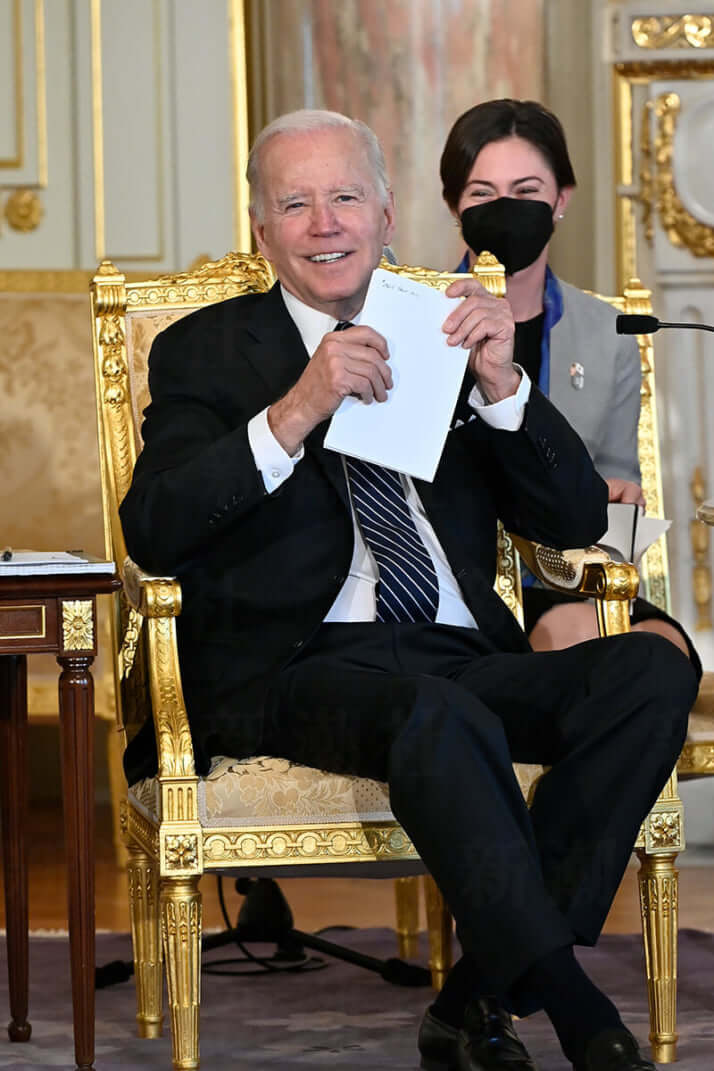7月に入っても絶好調 アメリカの株高はいつまで続くか
株式市場は堅調だが実体経済は?
米国の株式市場は7月に入り絶好調だ。
7月24日のダウ工業株30種平均は11営業日連続で上昇した。11連騰は約6年5カ月ぶりで、7月25日付の日本経済新聞は「企業決済や米景気に対する警戒感が和らぎ、投資家のマネーが株式に流入しやすい状況が続いている」とした。
【写真をみる】絶好調!なのに、実は米国で広まる“節約志向”の実態とは?
7月12日に発表された6月の消費者物価指数(CPI)は、前年比3.0%と12カ月連続で鈍化した。これを受けて、市場関係者の間で「米連邦準備理事会(FRB)の金融引き締めが想定より弱くなり、米国経済はリセッション(景気後退)を回避する」という軟着陸シナリオが勢いを増している(7月12日付日本経済新聞)。加えて、人工知能(AI)分野における米企業の高い将来性という追い風もある。
だが、実体経済は株式市場ほど堅調ではない。
7月24日に米S&Pグローバルが発表した7月の米国購買担当者景気指数(PMI)の(速報値)は、総合が前月比1.2ポイント低下の52.0だった。5カ月ぶりの低水準となり、サービス業の指数も2カ月連続で低下した。
7月25日付の日本経済新聞は「企業は景気見通しに対して慎重な姿勢を保っている」とした。この傾向が顕著なのは中小企業だ。
預金額は過去3年間の最低水準に
「銀行融資に頼る中小企業は急激な金融引き締めで弱っている」
こう指摘するのは、中前国際経済研究所代表の中前忠氏だ。
中小企業の苦境は雇用悪化に直結する。日本では中小企業の雇用数が全体の7割に上るが、米国でも従業員250人以下の中小企業が、民間部門全体の4分の3にあたる雇用を生み出しているからだ。米国の雇用環境が今後急速に悪化するリスクが高まっている。
中前氏は「経済分析を株式市場中心に行うとどうしても大企業中心となるが、これは現実の経済とかけ離れたものになる」と述べ(7月21日付日本経済新聞)、米国経済に対する楽観論に釘を刺している。
米国の国内総生産(GDP)の7割を占める個人消費の動向も芳しくない。
7月18日に発表された6月の小売売上高は、前月比0.2%増の6894億99 00万ドル(約95兆円)だった。3カ月連続で増加したものの、0.5%増という市場予想を下回っている。
気になるのは米国民の懐事情が悪化の一途を辿っていることだ。
米銀最大手JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)が英誌エコノミストのインタビュー(7月11日公開)で指摘したように、コロナ禍の巨額財政支援で米国の家計は潤ったが、その余剰貯蓄は年末で消失すると言われている。
国際通貨基金(IMF)によれば、現金給付や失業保険の拡大といった米政府による景気刺激策の規模は、2020年から2021年にかけて6兆ドル弱(840兆円)に達した。米国民がコロナ禍の行動制限下でその多くをため込んだおかげで、物価や借り入れコストが急上昇しても、支出を続けてこられた。
だが、その預金もそろそろ底をつくというわけだ。JPモルガン・チェース研究所によれば、預金額はピークだった2021年4月から3~4割減少し、過去3年間の最低水準に達してしている。
[1/2ページ]