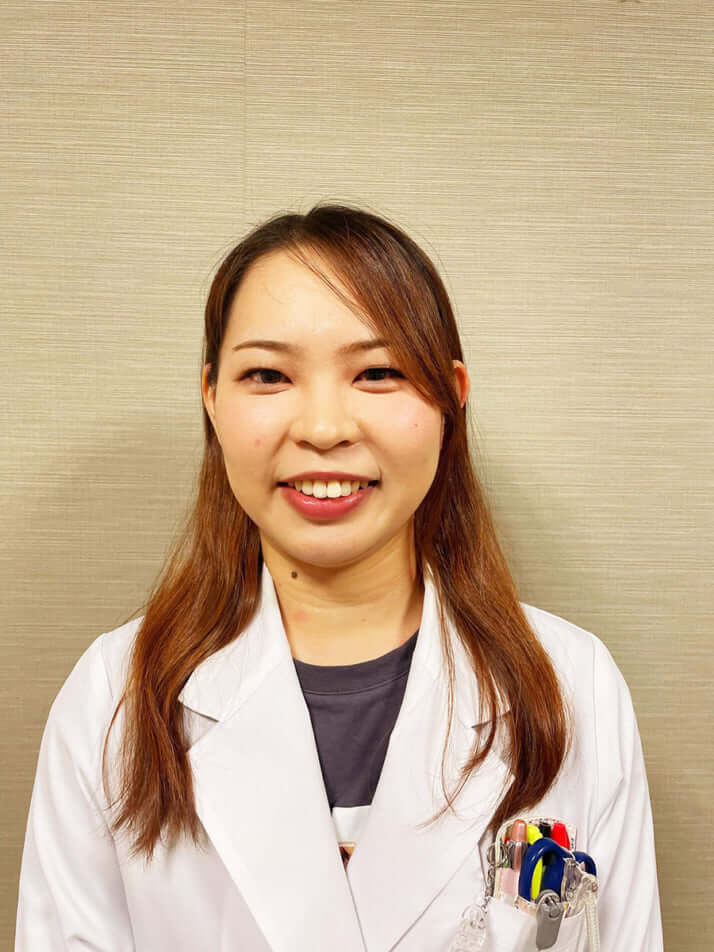薬は何種類から害になる? たんぱく質は1日何グラム必要? 高齢者に必要な「増食」「減薬」を指南
ポリファーマシーは必然
〈「薬」が「害」になりかねないポリファーマシー。その定義等について、熊本リハビリテーション病院薬剤部の薬剤師である松本彩加氏がより詳しく解説する。〉
国際的には5種類以上の薬を併用している状態がポリファーマシーであると定義されています。実際、5種類以上の薬を飲んでいると転倒の発生リスクが高く、また処方医がひとり増えると有害事象のリスクが30%増えるという研究報告もあります。
そして、厚生労働省の調査では、65~74歳の約3割が5種類以上の薬を併用していることが明らかになっています。私自身の経験でも、5種類以上の薬を服用している高齢患者さんは珍しくなく、圧迫骨折の90代の女性患者さんが、20種類以上の薬を持参されて驚いたこともあります。
このポリファーマシーは、現在の日本社会においてはある意味で当然の結果といえるのかもしれません。なぜなら65歳以上の方の62.8%がマルチモビディティ(多疾患併存)とされているからです。つまり、ポリファーマシーは高齢化に伴う必然ともいえるのです。
減薬が低栄養改善にも
ちなみに、皆さんお薬手帳は持っていらっしゃいますが、手帳用シールを貼らずに挟んでいるだけといった方もいて、自分がどれだけ薬を飲んでいるかをしっかりと把握できている方は半分くらいという印象です。
ポリファーマシーから脱却するためには、何よりも自分がどれだけの種類の薬を飲んでいるかを自覚し、その上で絶対に服用しなければいけない薬なのか、薬以外の対処法がないのかを、医師と相談しながら検討する必要があります。
とりわけ、代謝機能が衰え、薬のメリット以上にデメリットの影響を受けやすい高齢者には、あれもこれもという「足し算の思考」ではなく、副作用や飲み合わせといったデメリットを勘案し、不必要な薬は漫然と服用し続けないように心掛ける「引き算の思考」が重要になってきます。
なお昨年1月、英文誌「Nutrients」に論文が掲載された私たちの研究では、サルコペニアの患者さんが減薬すると栄養摂取量の増加につながることが明らかになっています。つまりポリファーマシーからの脱却は、低栄養改善にも役立つといえるのです。
とはいえ、日本では「お医者さま」という意識がまだ根強く残っており、処方された薬について医師に尋ねるのは何だか文句をつけているみたいでなかなか相談しづらい、という方もいるかもしれません。そういう方には、ぜひとも「疑義照会」という言葉を知っていただければと思います。
[4/5ページ]