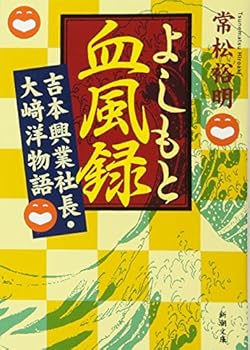吉本興業が東京で「弱小」だった頃
いわゆる「闇営業問題」に端を発した吉本興業をめぐる騒動で明らかになったのは、内部の関係者も、外野もそれぞれの「ヨシモト観」を持っているということだろう。昔ながらのファミリーだと捉えている者もいれば、単なる芸能事務所、一企業だと考えている者もいる。その違いがまた騒動を拡大するのに一役買っているという構図があるようだ。
こうした違いを生む原因の一つとしては、同社がこの数十年で急成長したことが挙げられる。今ではテレビ界、芸能界の本流にいるかのように見える吉本興業だが、東京進出は決してそう昔の話ではない。
漫才ブームで関西のお笑いが日本中を席巻していた頃には、まだ吉本興業は東京に拠点すら持っていなかった。現在の東京本部の源流となる事務所が設立されたのは、1980年、漫才ブームが始まった年だ。
これ以降の吉本興業の成長期を描いたノンフィクションが、『よしもと血風録 吉本興業社長・大崎洋物語』(常松裕明・著)。タイトルからもわかるように、最近とかく話題の大崎会長の年代記である。以下、同書をもとに吉本がまだ東京で弱小だった時代を見てみよう(引用はすべて同書より)。
「島流しもいいとこやないか」
1980年のある日、入社3年目の大崎氏は、上司に呼び出されてこう聞かれた。
「おまえ、東京、行くか?」
わけもわからぬまま「はい! ありがとうございます」と即答。
あまりの即答に上司は驚きつつ、こんな説明を加えた。
「実はな、今度、吉本が東京に事務所を作るらしい。その責任者として俺が東京に行くことになった。ついては、おまえを連れて行こうと思うんだが」
この上司は、やすし・きよしらのマネジャーとして有名な木村政雄氏。この誘いに大崎氏は、再度、
「はい! 分かりました!」
大きな声で返事をした。氏の頭の中には、流行の最先端としての東京のキラキラしたイメージや「大阪弁じゃない言葉をしゃべる可愛(かわい)い女の子もぎょうさんいるはずや!」といういささかよこしまな考えがあったようだ。
もっとも、社内の空気はそんな前向きなものではなかった。数日後、上京の準備をしている大崎氏に先輩社員が話しかけてきた。
「オマエも災難やなあ」
「えっ、何のことですか?」
「東京や、東京。島流しもいいとこやないか」
その先輩によれば、左遷に近い人事なのだという。大崎氏はこう述懐している。
「当時の吉本の考え方をひとことで言えば『劇場主義』だ。70年代の演芸ブームがそうだったように、『芸人はテレビやラジオで名前と顔を売って、劇場にお客さんを集めるもの。仕事になるなら東京でもどこでも行くが、あくまで稼ぎの本筋は大阪の劇場だ』という考えだ」
たしかに漫才はブームとなっており、その震源地は東京のテレビ局だった。しかしこのブームがどのくらいのものか、いつまで続くかはわからない。そのため、東京にできた拠点の正式名称は「東京連絡所」。つまり単なる窓口であって、事務所ですらないという位置づけだったのだ。大崎氏らの出発前に、当時の制作部長はこうクギを刺した。
「おまえら2人を東京に行かせるけど、あくまで連絡係として駐在させるんやから、ゆめゆめ自分たちで仕事をしたり、東京の放送局を開拓したりしようと思うなよ。芸人に花月の出番を休ませて東京に仕事に行かせることもならん。絶対許さへん」
事務所も大崎氏が個人の実印を押して保証人に
大崎氏が後で知ったところによれば、東京進出には上層部のほとんどが反対しており、賛成したのはこの制作部長らごく限られた人だったという。そのためか、赤坂のワンルーム事務所も、当初は会社ではなく大崎氏が個人の実印を押して保証人になったほどだったのだ。
しかしブームはことのほか拡大し、芸人たちの仕事は増える一方。当然、大崎氏の仕事も急増していく。問題は、彼らのフォローをすべき大崎氏自身、東京の地理すら把握していないようなレベルだったことだろう。テレビ局やスタジオの場所すらわからない。今と違ってネットで調べることもできない。頼れる仲間もいない。そのうえ怖い上司の木村氏からは「よそ様に弱みは絶対に見せるな」と厳しく教えられていたので、同業者に聞くこともできない。当時の雰囲気を大崎氏はこう振り返っている。
「テレビ局の楽屋でも僕一人だけが浮いていた。東京のマネージャーさんたちはみんなスーツに派手なネクタイでビシッとキメている。対する僕はヨレヨレのセーターにGジャン、おたふくソースのシミがついたようなチノパン姿。慢性の寝不足で顔はむくれあがり、髪もぼさぼさだ。(略)
周囲にいる他社のマネージャーや局の関係者、番組に出演するアイドル歌手まで、みんながクスクス笑っている気がした」
東京の放送局では大阪弁を聞くこともほとんどなかった時代だ。庶務の女性と軽口を叩くのがささやかな楽しみだったが、東京在住の彼女たちにとっても大阪や吉本のイメージはろくなものではなかった。
「大阪弁って、なんか怖いんですよね」
「そんなことあらへん。みんな優しいんやで」
「でも、先輩が言ってたんですけど、吉本って、やっぱりみんなヤクザなんですかぁ?」
テレビ局の人間に吉本の名刺を見せただけで、プッと吹き出されてしまう。「東京のテレビ局全体がそんな空気だった」という。
この80年は、漫才ブームのきっかけとなった「花王名人劇場」「THE MANZAI」の他、同じフジテレビで「笑ってる場合ですよ!」、日本テレビでは「お笑いスター誕生!!」が始まった年でもある。
翌81年にはあの「オレたちひょうきん族」がスタートし、芸人らの東京での人気はさらに勢いを増す。この勢いを受けてようやくこの年、東京連絡所は「東京事務所」へと格上げされるのだが、大崎氏自身は社内の事情や力学などで、82年、不本意な形で大阪に戻ることとなる。失意を抱えた彼が大阪で出会ったのが「ひときわ汚くて目つきの悪いコンビ」、のちのダウンタウンだった――。