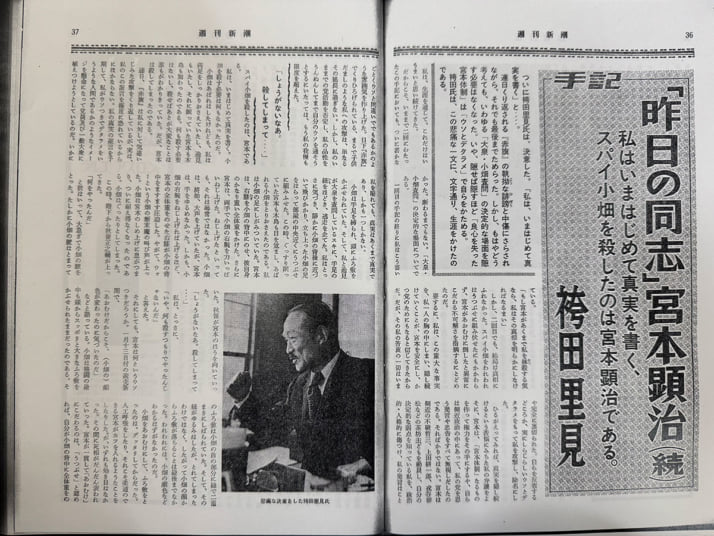95歳で死去「不破哲三氏」自伝が“天敵”の出版社から刊行された理由 知られざる“ペンネーム”の由来とは
ペンネーム「不破哲三」の由来
さっそく角谷さんの案内で、代々木の日本共産党本部へ、うかがいました。わたしは、その時点で入社20数年、週刊新潮記者も10年近くやってきた中堅です。しかしまさか、日本共産党本部のなかへ堂々と入る日が来るとは、夢にも思いませんでした。受付で「新潮社ごときが、何しに来たんだ」と追い返されるのでは――と、少々ビクビクしていました。
もちろん、そんなことはなく、不破さんはじめスタッフの方々は、ごくふつうに、ていねいに迎えてくれました。このとき不破さんはすでに75歳でしたが、声も外見もとても若々しかったのが印象的でした。
「あの~、ほんとうに新潮社からの刊行で、よろしいのでしょうか」と聞くと、笑いながら、「全然かまいませんよ。いい本にしましょう」と明るく答えてくれました。
インタビューは、全部で5回ほど、計15時間におよびました。全350ページ分の原稿を書きおこした角谷さんは、
「全体構成や目次立ても不破さんがつくり、語りは、立て板に水。見事でした。その後、書きおこした原稿にも、たいへん細かく直しを入れていただきました。インタビューの最終回では、奥様の七加子さんが『様子を見に来ましたよ』と、途中から入ってこられて、少々緊張したのを覚えています。どんな若造がインタビューしているのかを“偵察”に来たようでした(笑)」
『私の戦後六〇年』は、〈不破哲三〉のペンネームの由来からはじまっています。不破さんの本名は〈上田健二郎〉です。わたしは、このペンネームは、てっきり、赤穂四十七士のひとり、不破数右衛門からきているのだと、勝手に思い込んでいましたが、そうではありませんでした。
《〔鉄鋼労連の書記をつとめていた23歳の〕当時、自宅のすぐそばに“不破建設”なる名前のペンキ屋さんがありました。そこで働いていた四~五人の労働者の人たちが組合をつくることになって、妻の七加子(その頃、東京の南部で地区労の書記をしていました)が相談に乗っていました。そのペンキ屋さんの名前がヒントでした。「哲三」もあまり深い意味はなくて、つとめていた鉄鋼労連の「鉄」の響きを取った、その程度です。》(『私の戦後六〇年』より。以下同)
不破さんは子どものころからたいへんな本好きで、9歳のときに書いた冒険SF小説が、雑誌に掲載されたりしていました。父親が小学校の教員で、たまたま、作家の吉川英治を知っていたので、作品を読んでもらうべく、父子で訪ねたこともありました。戦時中は、典型的な軍国少年だったそうです。冒頭は、そんな微笑ましいエピソードがつづきます。
右翼が泣いて喜ぶ、日本共産党の主張
『私の戦後六〇年』は、基本的に、不破さんが自らの政治家人生を振り返りながら、戦後政治史を語っていく内容です。その大半は、日本共産党関係者や、政治史に詳しいひとたちにとっては周知の事実でしたが、一般読者には新鮮な内容が多く含まれていました。
そのひとつが、北方領土に関する問題です。北方領土とは、終戦時のドサクサで、ソ連(現ロシア)が不法占拠し、実効支配している、択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島の四島を指します。当然ながら日本政府は、四島返還運動をつづけているわけですが、日本共産党の主張は、そんな生易しいものではありませんでした。地図上でいうと四島のさらに上の得撫(ウルップ)島以北、カムチャッカ半島の手前・占守島までが日本の領土であり、そのすべてを返還せよと主張しているのです。
その根拠として、《幕末から明治にかけて、日本とロシアの間で行なわれた領土交渉の最後の通達点を、正確につかむことです。》と述べ、1855年(安政元年)と1875年(明治8年)の2回の正式交渉で決められた国境条約をあげています。
《〔この2度目の条約は〕「樺太千島交換条約」と呼ばれますが、(1)千島列島の得撫以北の部分も日本に引渡す、そのかわり、(2)日本がこれまで樺太にもっていた権利を放棄し、樺太全島をロシア領とすること、が主な内容でした。/大事なことは、この二つの条約は、ともに、二つの国の平和的な話し合いの結果、結ばれたものだということです。(略)その意味で、私たちは、この方面での日本の歴史的領土はどこかといえば、南北の区別なしに千島列島の全体が日本の歴史的領土に当たる、と考えています。》
この主張を意外と感じた読者も多かったようで、刊行後、「北方領土にかんする日本共産党の主張は、広く知られているのでしょうか。まさに右翼が泣いて喜ぶ主張ではありませんか」といった手紙が来た記憶があります。
本書中の圧巻は、やはり、国会における、時の総理大臣との激しい論戦の回顧でしょう。佐藤栄作をはじめ、俗に“三角大福”と呼ばれて政争を繰り広げた、三木武夫、田中角栄、大平正芳、福田赳夫ら、錚々たる顔ぶれと論陣を張りました。
近年は、重箱の隅をつつくような論戦が多く、いささかスケールに欠けるきらいがありますが、不破さんの時代は、実に迫力満点。日米核密約(核持ち込み)の暴露をはじめ、しばしば“スクープ”ともいえるネタをぶちまけ、総理大臣に迫る様子は、読んでいて実に痛快でした。ただし、自民党政治を批判するだけではなく、
《田中首相との論戦は、結構楽しいものでした。(略)論戦が終わると、質問者である私の席に寄ってきて、「今日はやられたよ」とか、論戦の印象について話し合う、これは、私の場合には、田中首相とともに始まった予算委員会の“よき慣行”でした。この“慣行”は、少なくとも七〇年代の歴代首相には、引き継がれていったと記憶しています。》
と、敵に塩をおくりかねないような思い出話も綴られています。
刊行後、ダメもとで「新刊発売の記者会見を開催したいのですが、さすがに新潮社内では、無理でしょうか」と提案すると「いいですよ、やりましょう」。なんと、日本共産党の現職議長が、新宿区矢来町の新潮社にやって来て、社内の小ホールで、マスコミ向けに記者会見を開くことになったのです。
新潮社には、よく、右翼や左翼などの団体が押しかけてきます。そのときも、総務部が「念のため、管轄の牛込警察署に警備の相談をしたほうがよいのでは」と言っていました。しかし、不破さんから「いや、ちゃんとこちらに警備がいますから、大丈夫です」とのことでした。
当日、黒塗りの専用車と、数人の私設SPらしき男性に警護されて、不破さんが、新潮社にやってきました。わたし自身が日本共産党本部に入ったとき以上に、このときのほうが、不思議な感動をおぼえました。全国紙の記者たちが詰めかけるなか、不破さんは、にこやかに本の内容を的確にまとめて、見事な宣伝コメントを語ってくれました。
記者のひとりが「なぜ、新潮社から刊行する気になられたのですか」と聞くと、「あまり深い意味はありません。ふだん、お付き合いのない版元さんから出すことで、わたしや党の考えを、さらに広く知ってもらえる機会になるのでは、との考えもあります」と、答えていました。
[2/3ページ]