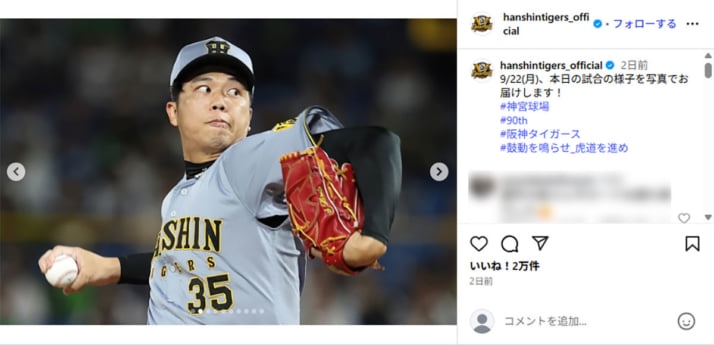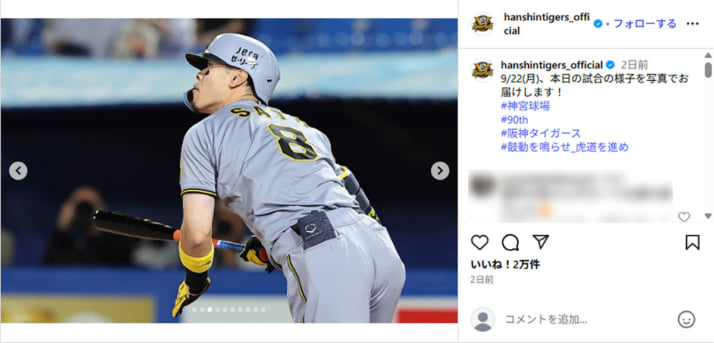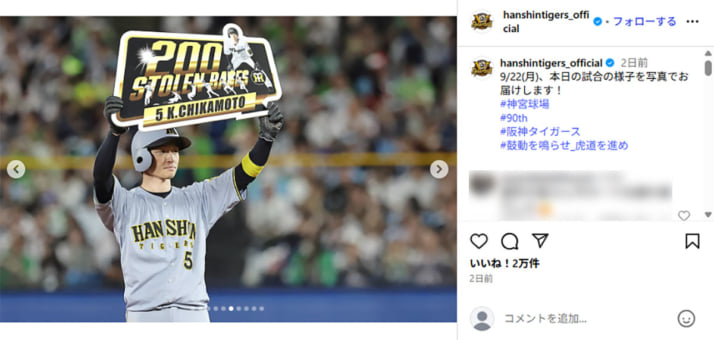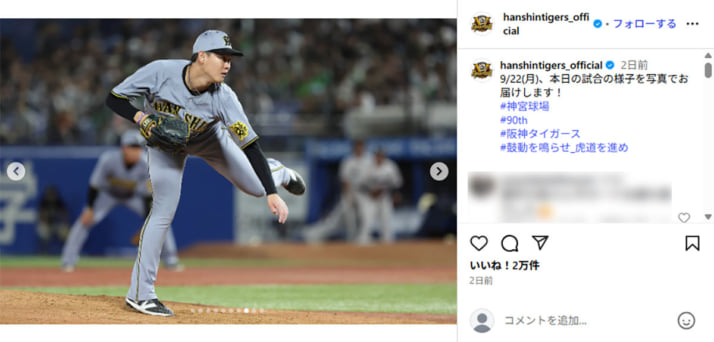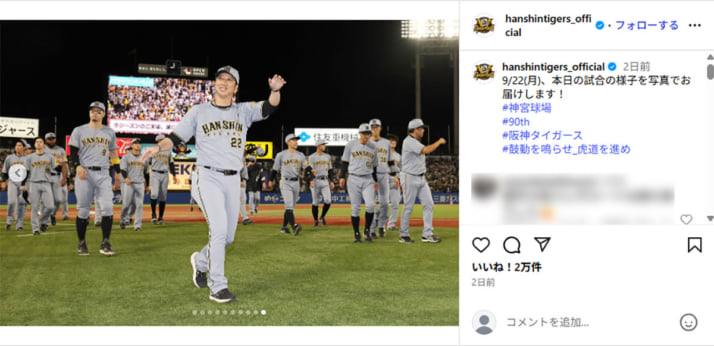ぶっちぎりでペナントを制するも…CSやプレーオフでまさかの敗退に終わった“悲劇の球団”
死んだふり作戦
最後に、昭和期のプレーオフで起きた逆転劇を紹介する。
2シーズン制が導入された1973年のパ・リーグは、前期優勝の南海が後期優勝の阪急を下し、リーグを制したが、シーズン総合成績では、阪急が2位・南海に9.5ゲーム差のダントツトップだった。後期も南海を12勝1分とカモにしていたにもかかわらず、絶対有利の状況からの大どんでん返しに泣いた。
10月19日のプレーオフ第1戦、「(初戦で)負けたら、ズルズルいってしまう恐れがある」と必勝を期した南海・野村克也監督は、シーズン中には見られなかった主力投手4人による継投で4対2と逃げ切った。
圧倒的有利の下馬評から、南海を呑んでかかっていた阪急は、初戦を落としたことにより、「絶対に負けられない」と意識過剰に陥っていく。
翌20日の第2戦は、阪急が9対7と打ち勝ち、対戦成績をタイに戻したが、22日の第3戦は江本孟紀を打ち崩せず、2敗目を喫し、後がなくなった。
それでも、2年連続王者の実績から、翌23日の第4戦は13対1と大勝。24日の最終戦は、満を持してエース・山田久志が登板した。
試合は投手戦となり、8回を終えて0対0。明暗を分けたのは9回だった。
山田の球威が落ちているのを見た野村監督は、本来なら守備固めを送る終盤に、代打出場のスミスをそのままレフトで起用しつづけていた。
そして、9回2死、そのスミスが右越え先制ソロ、次打者・広瀬叔功も連続ア
ーチをかけ、2対1で逃げ切り。「5試合で3勝すればいい」と短期決戦でも捨て試合をつくる合理的な戦い方が、7年ぶりの日本シリーズ切符につながった。
一方、南海の“死んだふり作戦”に翻弄された阪急の西本幸雄監督は「野村という男は、二刀流か三刀流(監督、捕手、4番)か知らんが、あれだけのチームを作り上げたとは、非凡な器だ」と最大の賛辞を贈っている。