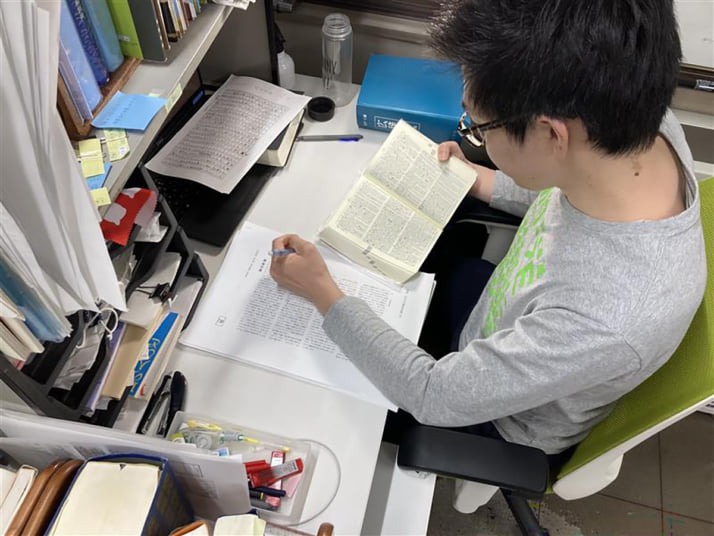校閲の大原則は「原稿を尊重する」だが…「修正すべき点に目をつぶってもいい」わけではない “校閲疑問は多い方がいいのか”問題を考える
こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。
今回もクイズから。
文化庁が毎年、「国語に関する世論調査」の結果を発表しており、当連載でも何度かその内容を取り上げています。
この調査の令和5年度版では、「悪運が強い」という言葉の意味についての調査結果が紹介されています。では、同調査内で「悪運が強い」の「辞書等で本来の意味とされてきたもの」は次のうちどちらでしょうか?
A……悪い行いをしたのに、報いを受けずにいる様子
B……悪い状況になっても、うまく助かる様子
【回答】皆さん、分かりましたか?クイズの答え合わせをしてみましょう
校閲者と伊佐坂先生が直接……?
さて、前回から「校閲疑問は多いほうが良いのか、少ないほうが良いのか?」という話をしておりますが、今回はその完結編です(まだの方は是非、先に前回の記事をお読みいただければ幸いです)。
前回の後半で、
・校閲者は、状況によっては校閲疑問の「書き方」や「量」を変えることがある。
・媒体やジャンルなどが変われば、校閲疑問の出し方も変わる。
ということをお伝えしました。しかし、ここで次のような質問が飛んできそうです。
「校閲疑問の整理は編集者がやるべきで、校閲は毎回同じようにやればいいのでは?」
確かに、"理論上"はそうかもしれません。編集者が校閲の疑問を補足、整理してから作家さんにゲラを渡す、というのは本来やるべき仕事です。
しかし、実は……。
この世には「編集者が中に入らない」、すなわち校閲が直接「書き手」に渡すゲラもたくさんあるのです……!
例として、週刊誌の「記者原稿」、すなわち特集記事やスクープ記事などは校閲が直接、記者(デスク)に校閲済みのゲラを渡します。内容について、口頭で話し合うこともよくあります。校閲とデスクの間に編集者的な役割の人はいません(小説やコラムには著者を担当する編集者か記者がつきます)。
また、週刊誌だけでなく、ほかの雑誌でも「編集者が書き手」というケースはたくさんあります。
「サザエさん」でたとえるなら、ノリスケおじさん(編集者)が不在の状態で、校閲者が直接、伊佐坂先生とやり取りしている、という構図になります。
また、新聞校閲も同様で、記事をまとめたデスクと校閲が直接やり取りします。書籍校閲なら、本の紹介文(帯のリード文)やコピー、プロフィールなどは編集者が「書き手」なわけですから、書き手と校閲が直接ゲラを渡し合います。間には誰もいません。
しかし、いくら「間に入っているから」といっても、編集者によっては……(字数の都合により以下略)。
[1/2ページ]