“友人の処刑”を見せられ失神 軟弱と見なされた王の真価を描き出した「たった一人の画家」
君主の“無言の苦しみ”を描きだした画家
古今東西に「名画」と呼ばれる絵は数多あるが、モデルを描いた作品は多い。ピカソには「7人のミューズ」がおり、女性が変わるたびに画風が変わったといわれ、日本では岸田劉生にとっての娘・麗子が著名だろう。モデルと密室で対峙する濃厚な時間は、画家に特別な刺激を与えるのだろう。
画家とモデルの関係は異性同士に限らない。ルネサンス時代のヨーロッパでは、君主が自身の権力を示すための肖像画を画家に発注する例が多かった。その場合、モデルは画家にとっては超のつく有力顧客ということになるので、独特な緊張感があったにちがいない。
本記事ではドイツ文学者の中野京子氏の著書『画家とモデル―宿命の出会い―』をひもとき、「大王」の尊称で知られるプロイセン王フリードリヒ2世と、彼の肖像を描いた画家メンツェルの不思議な関係を紹介しよう。
***
アドルフ・フォン・メンツェルは1815年、プロイセン王国ブレスラウ(現ポーランド)で生まれた(1905年没)。「フォン」はドイツ語における貴族の称号だが、これは晩年になって貴族に列せられてからのもの。身長140センチ足らずの矮躯(わいく)と大出世の組み合わせから、「ちびの閣下」とあだ名を奉られることとなる。
父親は石版画の工房を営み、メンツェルが15歳の時に家族はベルリンへ移住。大都市のほうがチャンスは多いし、才能ある息子にアカデミックな教育を施せるというのが父の思惑だったが、2年後には病没してしまう。メンツェルは弱冠17歳で工房を引き継ぎ、母や弟妹を養わねばならなくなった。
しかしメンツェルの強みは画才だけでなく、真面目で勤勉で努力を惜しまない点だ(それは生涯変わらなかった)。工房は父のいた頃同様に稼働し、まもなく王立芸術アカデミーへ通う余裕もできる。ただし通ってわかったのは、自分には硬直化した教授法など不要ということだった。以後、独学を貫く。
チャンスは意外なほど早くやって来た。プロイセンを大国に押し上げた英雄フリードリヒ2世(大王)の、即位100年にむけて刊行されたフランツ・クーグラー著『フリードリヒ大王伝』(1840~42年)に400点もの挿絵版画を提供したのだが、この本が大評判となり、無名だった若いメンツェルも人気画家の仲間入りするのだ。
さらにメンツェルはこれを機にフリードリヒ2世への強い個人的関心、ある意味、自分との共通項を見出し、大王を――とうに亡き人ではあったが――モデルにした油彩シリーズを次々発表してゆく。中でもっとも有名なのが《フリードリヒ大王のフルート・コンサート》で、この作品を知らないドイツ人はいない。他に《サンスーシ宮殿の円卓会議》や《ヨーゼフ2世との会見》などがある。
***
フリードリヒ大王の生涯はドラマティックなエピソードに満ちている。まず王太子時代。ドイツ諸国の各宮廷はまだ粗野で、酒と狩猟と女と軍事訓練に明け暮れていたのに、彼の嗜好は勉学とロココ芸術。フランス風にお洒落し、フルート演奏が趣味だった。そのため質実剛健を旨とする「軍人王」の父から「笛吹きフリッツ(フリードリヒの愛称)」「女の腐ったような奴」と罵られ、本や楽器を捨てられ、異常なまでに厳しく育てられた。
父王の怒りの根には、フリードリヒの同性愛疑惑があったようだ。無理やり縁談を進めると、あろうことか、この王太子は仲の良い臣下と国外逃亡を図る。たちまち捕まり、目の前で友の処刑を見せられ、失神。父に半ば監禁され、3年後には言われるまま政略結婚するが、妃にはついに指一本触れず、当然実子はいない。こうした事件は他国に筒抜けなので、28歳で戴冠した時(1740年)には与しやすい軟弱王としか見做されなかった。

プロイセンの軍人ハンス・ヘルマン・フォン・カッテ(1704-1730年)の肖像画(サンスーシ宮殿蔵)。後世「大王」と呼ばれたフリードリッヒ2世の王太子時代の親友で、国外逃亡を助けたことで死刑に処された。 (画像:Georg Lisiewski/public domain/Wikimedia Commons)()
新王となったフリードリヒは啓蒙君主を自称し、まずは拷問の廃止やオペラ劇場建設を発表して無難な船出と見せかけたが、同年末には宣戦布告もなくシュレージエン(ハプスブルク家の肥沃な領地)へ侵攻してヨーロッパ中の度肝を抜く。すぐ叩き潰されるかと思いきや、戦争に打ち勝ち、小さなプロイセンは大国となり、フリードリヒには「大王」の異名が付く。だが恨み骨髄のマリア・テレジアは、彼を別の名で呼んだ。曰く、「悪魔」「モンスター」「シュレージエン泥棒」etc.。
そんなこんなの合間には学者らを招いて首都ベルリンを「北方のアテネ」とし、『我が時代の歴史』をフランス語で執筆(当時の王侯貴族の公用語はフランス語)、夏の離宮サン・スーシ(無憂宮)をポツダムに建設、そこへヴォルテールを招聘し、また定期的にコンサートを開いて自らも作曲、演奏した。
マルチな才能の大王は、運の強さも証明してみせる。それは1756年、44歳の時に勃発した「七年戦争」だ。シュレージエン奪還を諦めないマリア・テレジア、新興国プロイセンの強大化を阻止せんとするロシア・ロマノフ家のエリザヴェータ女帝、及びフランス・ブルボン家(ルイ15世が政治に無関心なので戦争を進めたのは寵姫ポンパドゥール女侯爵)――この女性三人を中心としてフリードリヒ包囲網が整った。女性の下着の名をつけて「ペチコート作戦」と呼ばれたのがこれだ(大王の女嫌いはますます昂じたであろう)。
さすがのフリードリヒも戦が長引くにつれ敵の圧倒的動員数にじりじり後退し、とうとう敗けを覚悟して胸のロケットに毒薬を仕込んで自死も視野に入れたという。その土壇場でエリザヴェータが病没、甥のピョートル3世が王冠を被った。この無能な新帝はドイツで生まれ育ち、ドイツ人の血も流れていたことから、己をロシア人ではなくドイツ人と捉え、以前からフリードリヒ大王に心酔して自国の軍服をプロイセンと同じにするなど愚かも極まり、おかげで妃のエカテリーナ(後のエカテリーナ大帝)にたちまち暗殺される定めだったが、とりあえずロシアがプロイセンと同盟を結んでくれたおかげで大王は命拾いできたばかりか、戦後処理もうまくゆく。
その後もポーランド分割でさらに領土を増やし、資源も海外植民地も持たなかったプロイセンを確固たる列強の一員に据えて、文武両道の「偉大なるフリードリヒ」、教養あふれる「サン・スーシの哲学者」、愛すべき「老フリッツ」は1786年、大きな人気を保ったまま死去。人口と領土を2倍に、軍隊を2.5倍に、国庫を7倍に増やした46年間の在位であった(跡を継いだのは甥)。
***
――このような大王のエピソードの数々を油彩シリーズとして制作するにあたり、メンツェルは持ち前の研究熱心ぶりを発揮して資料を漁り、何度もサン・スーシを訪れ、建物の内外から当時の軍服や衣装、宮廷人らの肖像画まで調べて多くのスケッチを描き、さまざまなテーマで大王像を構築していった。
肝心のフリードリヒの容貌だが、実物を前にして描いた同時代の肖像の中では、スイス人画家アントン・グラフによる半身像、それも大王晩年の小型作品(後にヒトラーが官邸に飾る)以外、見るべきものはない。大王はさして特徴のある風貌ではなかったらしいが、ただ年齢のわりに若々しい大きな目を持ち眼光が鋭い。それが――ヒトラーの髭と同じく――大王を大王たる証とした。あとはプロイセンの軍服を着せれば、認識可能だ。
そうした老フリッツの顔を、メンツェルは《ヨーゼフ2世との会見》に活かしている。これは大王を啓蒙君主の鑑として尊敬し憧れたヨーゼフ2世が、やっと密かに会うことのできた瞬間を描いたもの。階段を駆け上がろうとする若いヨーゼフの胸の高鳴りまで聞こえてきそうだ。出迎える老王の余裕、プロイセン側の臣下の歓迎、対するオーストリア側の臣下の何とも言えぬ複雑な表情……。
それもそのはず。この時ヨーゼフ2世はマリア・テレジアとの共同統治者であり、母帝が大王を蛇蝎のごとく嫌っているのは承知の上での行動だった。メンツェルは、時代のスターたる大王が敵国の、しかもロシアに続いてオーストリアの君主までも魅了した事実を、大画面にドラマティックに描きだしたのだった(オーストリアは今も面白くはなかろう)。
この作品に先立ち、メンツェルが取り上げたのは壮年のフリードリヒ、真剣にフルートを奏でる芸術家としての姿だった。強い目の光にオーラがある。舞台は憂いを忘れさせてくれるサン・スーシ宮。登場人物のほとんどが特定できる。チェンバロで伴奏する大バッハの息子エマヌエル、右端に立つ王のフルート教師クヴァンツ、他にオペラ作曲家グラウンや軍人、大臣、科学アカデミー総裁、王の姉と妹、女官など(大王の妃は一度もサン・スーシに招かれなかった)。
ドイツ人はあらゆる芸術のうち音楽を最高位に置く「耳の人」たちだ。ラジオもレコードもない時代、音楽を聴くのに手っ取り早いのは自らが演奏すること。庶民もよく家族で合奏した。自らを「国民の僕」と呼んだフリッツもまた音楽に喜びを感じていたことを、メンツェルの絵画は改めて教えてくれた。この作品がフリードリヒ大王を語る上で欠かせないのは、そこから来ていよう(メンツェル80歳の時には、本作の活人画がサン・スーシで演じられた)。
一連の大王作品によって上層階級からの依頼が増え、また期待に十全に応えたことから、メンツェルには雨霰(あめあられ)と名誉が降り注いだ。王立アカデミー教授、功労賞、ベルリン大名誉博士号、枢密顧問官任命及び閣下の称号、最高位の黒鷲勲章(画家として初)、そして貴族の位……これらほとんど全てが彼を「愛国画家」と捉えた上での評価である。89年という長い人生で、優れた風俗画や風景画で労働者の実態や産業革命による変化なども描いているのに、まるで王家に媚びへつらって出世したかのように思われるのは不本意だったのかもしれない。晩年には、代表作の《フリードリヒ大王のフルート・コンサート》について、「シャンデリアを描きたかっただけだ」と言ったという。
だがたとえメンツェルの大王熱が時とともに薄れてゆき、現王家に対して批判的な思いも抱くようになったとしても、それでも一時は確かに自分と大王との間に共通項を見出していたのだ。それはいったい何だったのか。画家と100年前の君主。あまりに遠い二人の共通項とは?
一つには、生来的なことがハンデとなって女性とは縁がなかったこと。また同じ理由から画家は兵役を免除され、君主は直系の子孫を残せなかった。どちらも当時としては不名誉である。ピョートル3世やヨーゼフ2世には大王のそうした無言の苦しみをほんとうには理解できなかったろう、だが自分にはできる……メンツェルはそう思ったのではないか。
もう一つは、芸術へのたゆまぬ努力だ。君主は常に阿諛追従(あゆついしょう)に取り巻かれているが、大王はそこに安住せず、音楽という美を自分の力の限り追求し続けた。同じ努力家であるメンツェルはその点にも心打たれたに違いない。本作にはそれが反映されている。拝聴する臣下の中に音楽より天井の装飾に関心を持つ者がいたり、耳をすませるフルートの師が演奏に満足していない様子だったり……それはつまり大王の宮廷では、学問や芸術のもとでの身分差がなかったことを示している。
どんなにかメンツェルもこの場にいたかったことだろう。いや、彼はおそらく時を超え、この場にいたのかもしれない。
※中野京子『画家とモデル―宿命の出会い―』(新潮文庫)から一部を再編集。

![《ヨーゼフ2世との会見[部分]》](https://www.dailyshincho.com/wp-content/uploads/2023/03/2303170615_1-714x476.jpg)
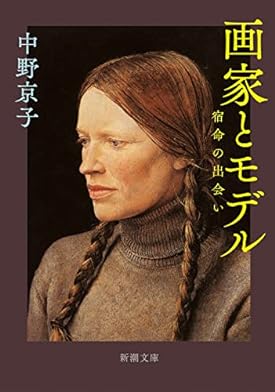








![《サンスーシ宮殿の円卓会議[素描]》](https://www.dailyshincho.com/wp-content/uploads/2023/03/2303170615_4-714x476.jpg)

![《フリードリヒ大王のフルート・コンサート[部分]》](https://www.dailyshincho.com/wp-content/uploads/2023/03/2303170615_6-714x476.jpg)
