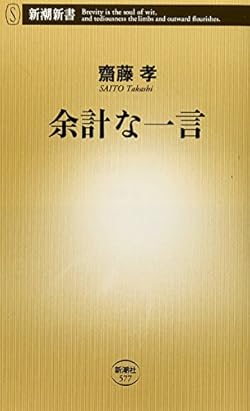「余計な本音」で秘書官を更迭になったエリート官僚は何を心得ておくべきだったのか
将来の次官候補だったのに
同性婚に関しての発言が問題視され、更迭された荒井勝喜・前首相秘書官は、悔やんでも悔やみきれないだろう。出世街道をまっしぐらに進み、経産省次官になるのも夢ではない立場だったのが、「オフレコ」で本音を語ったことで台無しになったのだから。
速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…
速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル
速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」
毎日新聞がオフレコを破ったことの是非はさておいて、荒井氏の危機管理が甘かったことは衆目の一致するところだろう。
かつてと比べて、問題発言の類が広げる波紋は大きくなっている。謝罪や撤回では事態がおさまらないことは珍しくない。とくに官僚や政治家といった公的な立場の人にはより厳しい目が向けられている――そんなことは常識のはずなのに、なぜうっかりと余計な一言を口にしてしまうのか(荒井氏の場合は余計な三言くらいかもしれない)。
コメンテーターとしても知られる齋藤孝・明治大学文学部教授は著書『余計な一言』の中で、ヒトはなぜつい余計な本音を口にしてしまうのか、その心理を分析したうえで、防止策を提言している(第2章 本音はいつも必要ではない)。
素人の毒舌は危険
齋藤氏がここで最初に取り上げているのは、「余計な毒舌」だ。ビートたけしや有吉弘行などの「毒舌」を見よう見まねで、スピーチに余計な「毒」を入れてしまったことで、場が冷え切ってしまう、といったケースである。
これについて、斎藤氏はこう語る。
「『毒舌』というのは、きちんと常識を踏まえ、あるいは場の空気が読めて、トークも上手であり、笑いを起こさせるプロの芸人だからこそつかえる技術です。社会で許される限度の気の利いた分量の毒でないといけませんし、この調合がとても難しい。素人は、基本的に真似しない方がよいのです」
要はヘタなウケ狙いは失敗のもと、ということだ。これは荒井氏というよりも、昨年問題になった牛丼チェーン役員の「生娘をシャブ漬けに」発言のほうが近いかもしれない。
荒井氏の場合は、どういうわけかはわからないが、本人が同性愛者に持つ本音を記者にぶちまけた、ということなのでサービス精神以外の動機があったとみることも可能だろう。
本音は我慢すべきもの
政治家の場合、こういう「本音」で問題を起こすことが度々ある。齋藤氏の分析は以下の通りだ。
「政治家はよく『本音』を漏らして問題になります。
特に太平洋戦争関連の歴史認識を巡っては、その種の失言騒動は後を絶ちません。本書では、誰の歴史観が正しいとか、間違っている、という議論には踏み込みません。
ともあれ、多くの場合、政府の方針とは別に、その政治家が信念として思っていることがあり、その人が信じる『歴史の事実』を『本音』として口にすると、政治問題化するという現象はよく見られます。
おそらくこういう人は、『本当に思っていることを黙っているのは、何だか不誠実な気がする。この本音を隠しもつのはいけないのではないか』と思って、溜めこんでいたものを吐き出すように、本音を漏らしてしまうのでしょう。『王様の耳はロバの耳』という寓話(ぐうわ)と同じことです」
本来、荒井氏は記者に問われても自分の内心を吐露する必要はまったくなかった。それはオフレコでもオンレコでも同じことである。
しかし、なぜか記者相手にためこんでいたものを吐き出してしまったのだ。
齋藤氏はこう戒める。
「そういう気持ちは人間に共通のものなので理解はできます。しかし、そもそも政治家に求められる資質として、『話したくても話してはいけないことを、話さずに我慢できる』という精神的な強さも含まれているはずです。本音を言ってスッキリする職業ではなく、むしろ逆なのです。もしもどうしても吐き出したいのならば、家庭など完全に秘密の守れる場でやるべきです。
もう一つ、本音を言うことにはさしたる意味がない、という認識も必要です。本音を言わないと気分が悪い、不誠実な気がすると考える人は、その本音イコール自分であると思ってしまっています。しかし、その『本音』だと思っていることだって、永久不変とは限りません。いま『本音』だと思っているものも、新しい情報が一つ加わるだけで、ガラッと変わってしまうかもしれません。絶対の真理だと思っているけれど、表面的な好き嫌いや思い込みや偏見だということもよくあるのです。
ほとんどのことは『本音』ではなくて、あくまでもその人の『現在の認識』もしくは『一つの認識』に過ぎないと思ったほうがよい。それは刻々変化するものなのです」
不寛容な社会だと認識する
更迭という事態によって荒井氏の「認識」が変わったかどうかは定かではないが、一方でこうした発言が大事になる風潮を憂う声もある。何でもすぐに「炎上」となり、「責任を取れ」となることがいいのか、ということだ。
これについて、自身、コメンテーターでもある齋藤氏はこう語っている。
「職場や学校でもそうなのですから、テレビのように発言がより広範囲に影響する場では、個人の性的な好みとか、女性の容姿について安易に発言するのを、意識的に避けていかなくてはならなくなりました。
不用意な発言が、その部分だけ切り取られて、ネット上ですぐに広まってしまい、引用に次ぐ引用の末に、みんなが知る大問題になってしまうのです。
そのため、世間とは少し違う角度からの発言をする際には、それなりのリスクを伴うという覚悟が必要です。私もコメンテーターとしては、そのあたりの境界線を考えながら話すように心がけていますが、社会がどんどん『不寛容』になっていることを実感しています。
(略)
私は、ちょっとした一言が許せないという風潮が行き過ぎることは問題だと思っています。本来、利害関係者でも何でもない人たちが、『許せない』とネットで騒ぎ立てることが増えています。些細な失敗や不祥事に対して、『絶対許せない』『もう消えてしまえ』『芸能界追放だ』など、過激な言葉で攻撃するようになっています。自分と関係のないことに対してもとことん責め立てるという過剰な攻撃衝動が募り、不寛容な態度が蔓延して、世の中が窮屈になっているようにも思えます。
このような風潮に変化が起きることを祈っていますが、あえて火中の栗を拾う必要もありません。テレビのコメントと同様に大学でも、講義などの際に、自分で言葉をチェックするフィルターがより多くなりました。万が一にも誤解を招く言い方でないかどうか、いつも検討しています」
同書で齋藤氏は「言葉のディフェンス力」を強化する大切さを説いている。現代人にとって格段に必要な能力なのだ、という。
防衛力増強を訴えているわりに、岸田内閣には足りない能力なのかもしれない。