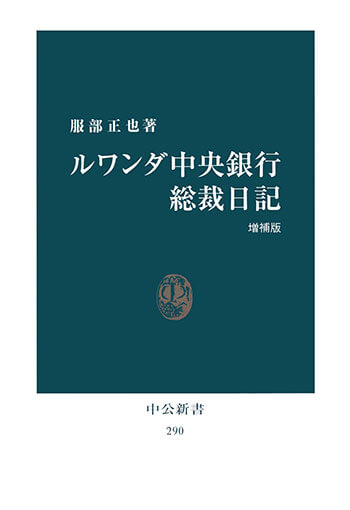50年前、アフリカ「ルワンダ」へ渡り、たった一人で財政を再建した日本人の物語
50年近く前に出版された『ルワンダ中央銀行総裁日記』(中公新書)が、今、書店に平積みされ、30代を中心にした若い世代に爆発的な人気を呼んでいる。日本人が国際社会で活躍することなどまだ稀だった1965年、日本銀行に勤める46歳の服部正也氏が国際通貨基金(IMF)に出向、IMFからアフリカ中央の小国ルワンダへ中央銀行総裁として派遣された際の回想録である。
***
速報「“私に恥をかかせるな”と言ったよね」 高市首相の“パワハラ上司発言”の狙いを旧知の元議員が解説 「恐怖心を閣僚に植え付ける目的があったのでは」
〈自分が生きてゆけないわけはない〉
初版は1972年6月。一度は品切れ重版未定になったものの、復刊を強く望む声があり、94年に起こった「ルワンダ動乱」への論考や、服部氏の長女の夫で、日銀の後輩でもある大西義久氏(73)による服部氏の「開発援助哲学」を加筆し、2009年に再刊行されたという。筆者はすでに1999年に故人となっているが、「いつの時代に読まれても現代的意義がある」(担当編集者)ことから、長い間読み継がれてきた。中央公論新社の若手営業部員らが、「もっと多くの人にこの書籍のおもしろさを伝えたい」と奮起。昨年11月にプロジェクトを立ち上げ、手作りのポップ作成などを経て、今年2月から本格的に拡販を開始すると、瞬く間にSNSなどで評判が広がり、わずか3ヵ月で9万部の増刷となった。
服部氏が赴任した当時のルワンダは、ベルギーから独立して3年あまり。日本はおろか、IMFでもルワンダに行った人はほとんどおらず、得られた断片的な情報では〈ひどく貧乏な国で生活環境が悪い〉国だったが、服部氏は〈生活条件の悪い国こそ、外国人技術援助の意味もあると思っていたし、また、現に人間が住んでいるところなら、自分が生きてゆけないわけはない〉〈しかしなんといっても日本銀行員として、小さくても中央銀行の総裁になることはうれしいことである〉と、総裁就任を引き受けた。
しかし、恒常的な“超”財政赤字を抱える国の経済を再建することは困難を極めた。中央銀行でさえ破綻寸前の資産状態で、行員は派閥を作り働かない。政治家ですら経済の窮状を理解しておらず、ルワンダに関わる外国人らは自分たちの利権を手放そうとしない――。まさしく八方塞がりの状態だった。
生活環境も劣悪だった。空港にはビルはなく、あるのは検疫と入国管理の事務所である電話ボックスのような2つの小屋。道路もほとんど舗装されておらず、首都のキガリでさえ商店といえるほどのものは数軒しかない。停電や断水はいつものことで、水道をひねるとダニの浮いた水が出ることもしょっちゅうあった。普通の人なら絶望しそうなものだが、服部氏はまったくひるまない。豪放磊落ながらも細やかな気遣いと抜群の行動力で、最悪とも言える状況をぐいぐい切り開いていく。
[1/2ページ]