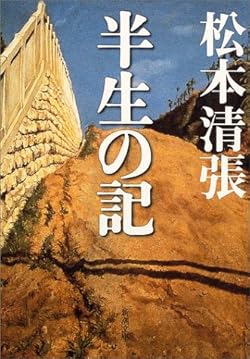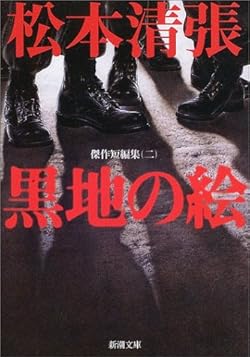250人の黒人兵が町を襲った 「松本清張」が掘り起こした、知られざる「小倉米兵脱走事件」とは?
今年は数々の名作を遺した松本清張の生誕110周年。「砂の器」「点と線」「ゼロの焦点」など社会派と呼ばれるミステリ作品を描いた清張だが、実はあるひとつの米軍にまつわる事件が、清張によって掘り起こされていたことはご存じだろうか。
今であれば確実にニュースとして世に知れ渡っていたはずだが、事件が起こった当時の日本は1950年のアメリカ占領下。各地には「進駐軍」の基地が置かれ、全国に最大で40万人の兵士が駐屯していた。報道管制が敷かれた当時の日本では、米軍に都合の悪いニュースはもちろん御法度。新聞などでも一行の記事にすらなっていない。
しかし清張が記した『半生の記』には。その当時のことが克明に描かれているのだった。(以下引用は同書より)
***
事件は今から69年前の7月11日、夜半に発生した。北九州・小倉には米軍の城野補給基地(旧・日本陸軍補給廠)がおかれていたが、そこから米兵たちが集団で脱走したのだった。脱走したのはほとんどが黒人兵で、約250名との記録がある。
速報中国人観光客の減少に「ずっとこのままでいい」 京都では喜びの声が 一方、白川郷では「墓に登ったり、私有地で用を足したり…」 地元住民は嘆息
速報「月給20万円のほとんどを詐欺につぎ込み…」 ロマンス詐欺を巡って逮捕の僧侶は「詐欺被害の常連」だった だまされ続けた“複雑な事情”とは
カービン銃などの自動小銃を所持、手榴弾を基地から持ち出したツワモノさえいた。軍服に完全武装の兵士たちは夜陰に乗じて小倉市内広域に散り、繁華街や民家を襲撃。住民に対し集団暴行、破壊、略奪、等々の狼藉を繰り返し働いていた。
そして、この事件に間近で遭遇した人物がいた。当時40歳の松本清張である。作家としてデビューする前のことで、朝日新聞西部支社広告部に勤務していた。清張は小倉で生まれ、小倉で育っている。しかも家族と共に暮らしていたのが、城野補給基地のすぐ横にあった集合住宅だった。
事件の翌日にその事実を知った清張は、回想録でこう書いている。
〈昨夜、すぐ近くのキャンプ(注・米軍基地のこと)から黒人兵が集団脱走し、この住宅を初め近在の民家に押し入り暴行を働いたというのだ。近所の話では、4、5人ずつ武装した黒人兵が店に押し入り、その辺の酒をタダ飲みしたうえ、棚にあったウイスキーをごっそり持ち去ったという。ある家では亭主が銃の台尻(だいじり)で殴られ、ある家では主婦が強姦(ごうかん)されたといっていた〉(1966年刊『半生の記』)
米兵たちは脱走には、基地内の庭から道路脇(わき)の溝に通じている排水用の土管を使っていた。それもまた、清張の生活圏にあった。
〈この土管は私もそこを通るたびに見ている。黒人兵に限らず、それまでは兵隊は深夜たびたびそこを脱け出ては女の家に泊り、翌未明にまた土管をくぐって営内に戻る。夜歩いていると、そういう兵隊の影にたびたび出遇ったものだった。黒人兵の集団脱走はそれを利用したのである〉(同書)
脱走兵たちの鎮圧のために、この日、米軍からは2個中隊までが出動しているが、こうした事実は占領下の日本にあって、まったく報道されなかった。が、鎮圧部隊と脱走兵との銃撃戦もあった史実が、清張の記録から分かる。
〈昨夜はピストルの射(う)ち合いがあり、照明弾が射ち上げられたりして、まるで市街戦だったと言っていた。偶然そこを通りかかった通勤者の話だが、MP(注・アメリカ陸軍の憲兵)が道の途中にいて、そこを通ってはならぬといったという。横を機関銃を据えつけたジープが何台も疾駆していたそうである〉
妻を犯された男のすさまじいまでの復讐を描く「黒地の絵」
8年後、この米兵集団脱走事件をもとに、清張が書き上げたのが短篇小説「黒地の絵」だ。清張は執筆にあたり、綿密な取材を敢行したと言われている。そしてこの作品により、「小倉米兵集団脱走事件」は世に知られるようになったのだった。
鎮圧部隊と脱走兵たちとの銃撃戦の様子を、清張は同作でこう描写する。
〈2個中隊の鎮圧部隊が次に出動した。彼らは装甲自動車と、20ミリ口径の機関砲を積んだジープを走らせた。部隊の打ち上げる照明弾が夜空を照らし、両軍の射ち出す機関銃、自動小銃の弾曳(だんえい)は赤く尾をひき、銃声は森閑とした周囲6キロの地域に聞こえた〉
小倉での米兵集団脱走事件の遠因は何だったのか。米軍は劣勢の続く朝鮮戦争の戦局を挽回すべく、日々、大量の兵を日本から送り続けていた。城野補給基地には他の基地から補充部隊が到着しては、数日の滞在を経て、戦地に向け旅立っていった。清張はその姿を冷静に見つめていたのである。
脱走事件を起こした米兵たちの心理を、清張は次のように汲み取り「黒地の絵」の中でこう綴っている。
〈大田(タイデン)を放棄し、光州(クァンジュ)を退却し、西南部からも圧迫をうけ、米軍は釜山の北方地区に鼠(ねずみ)のように追いこまれていた。そこにこの黒人部隊が投入される予定だったのだ。戦地に出動するまで5日と余裕はなかったに違いない。そのことは彼らが一番よく知っていた。彼らが共産軍の海の中に砂のように没入してゆく運命であることも〉