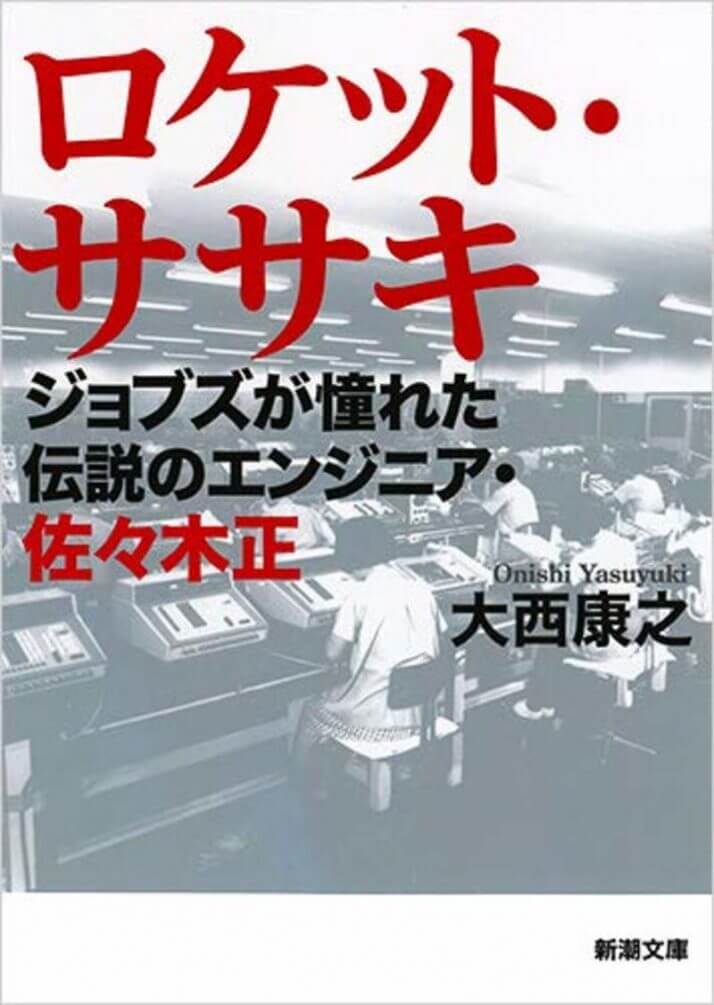『ロケット・ササキ』外伝(1)「電子レンジ」開発に携わった「寺師一清」
1953年に大阪府立大学を卒業した寺師一清(てらしかずきよ)は「実家から通える」という理由で早川電機工業(現シャープ)に入社した。大卒入社の1期生で同期は13人いた。大学で機械工学を学んだ寺師は研究所に配属された。
その年の2月に『NHK』のテレビ放送が始まった。売れるかどうか分からなくても、いの一番に製品化し、世間から「ハヤカッタ電機」と冷やかされていた早川電機は、放送が始まる前に電機業界の先陣を切って家庭用テレビの量産に踏み切った。
車より高い調理器
「期待の新人」寺師は、続々と開発される新型テレビのシャシー(枠組み)設計を担当した。
1958年になると寺師は平野工場(大阪市)に移った。平野工場はテレビのほか、冷蔵庫、蛍光灯、炊飯器を生産しており、寺師は掃除機やミキサー・ジューサーの開発に携わった。翌年には製品企画部長に抜擢された。入社6年目で部長というのは超スピード出世に思えるが、大卒1期生の寺師たちは入社当初から「幹部候補」であり、ベンチャー・スピリットに溢れる社内では、「当たり前の人事」と受け止められた。
「何でもいいから、どんどん新規商品を考えろ」
担当役員にハッパをかけられた寺師たちは、思いつくままに様々な試作機を作った。
例えば「ゼンマイ式髭剃り」。コンセントも電池もいらないのが売り物だったが、ゼンマイの力では刃を素早く動かすことができず、まともに剃れないため製品化は見送られた。「電動ハサミ」は洋裁で大量に布を裁つ縫製会社向けに開発した。1枚の布なら鮮やかに切れたが布を重ねると切れず、これもお蔵入りとなった。
失敗が続く中、唯一、製品化にこぎつけたのが「レーダーレンジ」である。レーダー、すなわち電磁波で食べ物や飲み物を加熱する調理器だ。本家の米国ではそう呼ばれていたが、「レーダー」では物騒なので「電子レンジ」として商品化することにした。レーダーレンジのアイデアを早川電機に持ち込んだのは、電磁波を発生させるマグネトロンという部品を作っていた神戸工業の佐々木正という取締役だった。
佐々木は戦時中、陸軍登戸研究所に徴用され、マグネトロンを使った「殺人光線」の開発に携わっていた。戦後、佐々木は米国のリットンという会社がマグネトロンを民需転換してレーダーレンジを作っていたのを目の当たりにし、すぐに神戸工業で事業化に動いた。それに、最初に食いついたのが「ハヤカッタ電機」の早川電機だった。
1962年、早川電機が発売した本邦初の「電子レンジ」の値段は54万円。トヨタ自動車の大衆車「パブリカ」が38万9000円の時代である。今の価格にして200万円近くにもなる。車より高い調理器が家庭に売れるはずがない。
寺師は海苔や昆布の乾燥用にどうかと漁村を回ったが、「そんな高いもんが使えるか」と門前払い。ようやく見つけた最初の客は、近畿日本鉄道(近鉄)だった。近鉄は特急列車のビュッフェに電子レンジを導入した。安全のため列車の中で火は使えないが、電子レンジなら火を使わずに温かい食事を提供できるという算段だ。
次に見つけた顧客は1964年、東京オリンピックの選手村である。こちらも安全上の配慮から、なるべく火を使いたくない。早川電機の電子レンジは、世界中から集まるアスリートに、いつでも暖かい料理が食べられるという「おもてなし」を提供した。
激烈な「電卓戦争」
1964年の春、神戸工業の佐々木が早川電機に移籍した。コンピューター、半導体への進出を夢見た創業者の早川徳次と2代目社長の佐伯旭が、三顧の礼で引き抜いたのである。
佐々木が早川電機に移る数年前から、米国では企業が給与計算や経理にメーンフレームと呼ばれた大型汎用コンピューターを使い始め、IBM、バローズ、ユニバックといったメーンフレーム・メーカーが台頭していた。
日本の通商産業省(現経済産業省)もコンピューター産業の育成に乗り出し、富士通、NEC、日立製作所、東芝、三菱電機、沖電気の6社を重点的に支援することになった。早川電機も手を挙げていたのだが、東京に嘆願に行った早川徳次は、通産省に「おたくの体力では無理ですよ」といなされ、怒り心頭に発して大阪に戻ってきた。徳次は幹部を集めて宣言する。
「読み書き算盤を電子化せよ。早川電機は、大企業が使う大型コンピューターはやらない。その代わり八百屋のおかみさんが使える小型コンピューターを作る」
こうして個人向けの計算機「電卓」の開発が始まり、若手の技術者たちが初めて触るコンピューターと格闘しているところ、やってきたのが電子工学の第一人者の佐々木だった。
佐々木は「商用化は不可能」とされていたMOS(金属酸化膜半導体)で電卓用のLSI(大規模集積回路)を作り、初期には何十キログラムもあった電卓をポケットサイズに小型化した。佐々木率いる早川電機は、樫尾4兄弟のカシオ計算機と激烈な「電卓戦争」を繰り広げ、その過程で50万円を超えていた価格は、十数年で1万円を切るまでになった。
電卓の小型化に飽くなき執念を見せた佐々木は、ディスプレーに液晶を採用し、乾電池の代わりに太陽電池を取り入れた。いずれのデバイスも民生機器で採用するのはこれが初めてだった。
「スケールの大きな日本人」
佐々木が商用化を実現したMOS・LSIはアポロ12号にも採用され、佐々木とシャープ(1970年に早川電機工業から社名変更)は米国航空宇宙局(NASA)から「アポロ功労賞」を授与されている。アポロに搭載するMOS・LSIは着陸船の開発を担当した米ロックウェル社との共同作業だったが、ロックウェルの技術者たちは、あまりに大胆な発想をする佐々木に終始振り回され、いつしか佐々木のことを「ロケット」と呼ぶようになった。
電卓戦争が終わると佐々木は東京支社長になった。寺師は秘書役として、東京で佐々木の身の回りの世話をすることになった。佐々木は毎朝7時からホテルニューオータニで朝食を食べる。シャープの取引先だけでなく、各国の大使や日本に駐在している各国のジャーナリスト、政治家、通産省の役人、ベンチャー経営者など様々な人々が「ロケット・ササキ」のアドバイスを求めてニューオータニにやってきた。
「ああ、その部品ならあの会社に頼めばいい」
「だったら銀行を紹介してあげるよ」
夜はニューオータニの地下にあるクラブの1室が佐々木専用になっており、チビチビとカンパリソーダを舐めながら、よろず相談に乗った。議論が白熱すると会食が午前0時を過ぎることもあり、そんな時、佐々木は「寺師くんも泊まっていきなさい」と言うのだが、寺師は「僕は経費で落とせませんから」と、自腹を切ってタクシーで帰宅するのが常だった。
佐々木は専務時代、米カリフォルニア大学バークレー校の学生だった孫正義が発明した電子翻訳機のライセンスを1億6000万円で買い取り、それが後にソフトバンクの開業資金につながっていく。佐々木は2018年、102歳で亡くなったが、孫は最後まで佐々木を「大恩人」と呼び、礼を尽くした。アップル創業者のスティーブ・ジョブズも、アップルを追い出された不遇の時代に東京・市ヶ谷のシャープ東京支社を訪ね、佐々木に助言を求めている。
そんな佐々木を間近に見てきた寺師は言う。
「日本にとどまらず、世界中どこにでも知り合いがいて、どんな人にも助けの手を差し伸べた。あんなスケールの大きな日本人は後にも先にも見たことがない」
佐々木の波乱万丈の人生については、3月28日に発売された評伝『ロケット・ササキ ジョブズが憧れた伝説のエンジニア・佐々木正』(新潮文庫)をご覧ください。