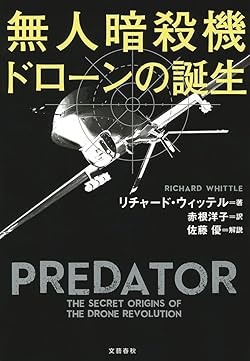最新兵器の裏にある人間ドラマ/『無人暗殺機 ドローンの誕生』
イラク戦争の伝説的狙撃手を主人公にしたクリント・イーストウッド監督の新作「アメリカン・スナイパー」を観ていたら、不意打ちのように米軍の無人機が出現した。緊迫した接近戦の上空を、ゆっくりと浮動する、頭でっかちなその姿は夢幻的であり、牧歌的である。地上の苛烈な戦闘とは異次元の物体で、フェリーニの映画に彷徨い込んだような錯覚に、一瞬襲われた。
この無人機は暗殺用ではなく、偵察用であろう。無人偵察機から送られる画像に助けられて、主人公たちは上官から脱出先を指示され、なんとか危地を脱することができた。この一事を以てしても無人機の効能は明らかだが、二十一世紀の戦争の形を変えてしまった兵器の本領は、そこにはない。
本書の中で「大陸間スナイパー・ライフル」と形容される無人暗殺機は、「地球の反対側から、敵の様子をライブでこっそり観察」しながら、テロリストに照準を合わせ、レーザー誘導ミサイルを発射する。ターゲットを長時間にわたって監視した末に、エアコンがよく効く施設から、炎熱の砂漠へと発射される最新兵器である。本書はその四十年に及ぶ開発物語なのだが、夢と感動のプロジェクトXではない。一人の模型飛行機好き少年から始まったアイディアが、転々と何十人もの手をわたるうちに、変身し、変異し、変貌する過程をドラマチックに描いたノンフィクションなのである。
最初の一歩は、イスラエルの「小柄で青白く童顔の」航空技師カレムから始まる。戦闘機の改良でイスラエル防衛賞を三度受賞した天才技師は、自分の会社を興し、高性能の武装無人機開発に没頭する。滞空時間を飛躍的に伸ばし、国境を昼夜警備できれば、祖国防衛の切り札となるはずだった。
この愛国者の期待は裏切られる。政府と軍は性能の良否にかかわらず、カレムの会社から兵器を購入する意思はなかった。祖国に見切りをつけ、カレムはビジネスチャンスを求めてロサンゼルスに移住した。自宅のガレージを仕事場にして、飛行機製作を試みるカレムに資金提供をする人物が現われるのがアメリカという国である。二人の有能な助手を雇って開発を続け、四十八時間操縦可能な、誰にも予想しえなかった無人機が出現する。
カレムの会社は順調に見えたが、そうではなかった。権謀術数渦巻く兵器調達の世界は、「性能よりも政治やコネで決まる」ことが多かったからである。無人機の予算が半額にカットされるという逆風の時期でもあった。「墜落」寸前の無人機技術を買収する兄弟がここで現われる。「麦わら帽子は必ず冬に買え」を投資のモットーにするブルー兄弟は、誰も見向きをしなかった技術に注目する。兄弟はもともとGPS受信機を自動操縦装置につなぎ、無人機の機首にTNT爆弾を搭載し、コストダウンに成功すれば、それは「貧者の巡航ミサイル」になるというアイディアを持っていた。兄ニールはドイツ出身の妻が体験した無差別爆撃の恐怖も、そして共産主義者の侵略も阻止しうる無人機の必要性を確信していた。「政府の関与なしに自力で」無人機を開発したい兄弟にとって、カレムの発明品はおあつらえの安い買い物だったのだ。
状況は一九九二年に起きたボスニア紛争で一変する。CIA長官ウルジーと統合参謀本部議長パウエルが、無人機の活用に興味を示す。偶然にも、ウルジーは弟リンデンともカレムとも知り合いだった。事態は急を要し、悠長に開発をしている余裕はなかった。半年で納入すると兄ニールは確約する。
ここからが開発物語の本編である。さまざまなキャラクターが実用化までに関与する。上は大統領から、下は現場の一兵卒まで。現場では、開発精神と技術の手渡しのリレーが行われる。「脳みそが二つある男」と呼ばれるペンタゴン職員は、無人機からの映像をペンタゴンの幹部に生中継するアイディアを成功させる。アグレッシブなCIA副長官アレンは、ビンラディン暗殺に使えると直観する。白いローブ姿のビンラディンを実際に発見できた。通信スペシャリストの一等軍曹は、家電量販店に行き、十二ドル九十五セントの固定電話用ヘッドセットを買って、自分で工作し、ターゲットの会話をキャッチすることを可能にした。こうした個性的な脇役たちがアメリカという国の精神をビビッドに伝えてくれる。
全編に「規則の範囲内で創造的に行動する」精神は脈打っている。その一方で、新しい兵器ゆえの規則との抵触という問題が起きる。無人機の武装化の前には、空軍の法律顧問から「連邦議会の承認がいる」との意見が出される。無人機の地上誘導ステーションはCIA本部に置かれるが、発射のスイッチをCIA職員が押せるのかが問われる。無人機からの発射は暗殺なのか、それともテロに対する正当防衛なのか。ブッシュ大統領が「大統領行政命令の暗殺禁止を緩和し、アルカイダを崩壊させるための致死的秘密作戦の権限をCIAに与える旨を通知する覚書」に署名することで問題はクリアされた。
暗殺無人機は戦争と倫理をめぐる新しい難問をこれからも発生させるだろう。この新兵器が誰によってどんな使われ方をされていくのか、予想はつかない。
実戦での発射に初めて成功した時のことである。この作戦が映画化されたら誰が自分の役を演じるかで、ひとしきり冗談が飛びかった。しかし、地味で、ひたすら忍耐を要求される、昂揚感の少ない作戦を、ハリウッドが映画にするのは難しいのではなかろうか。