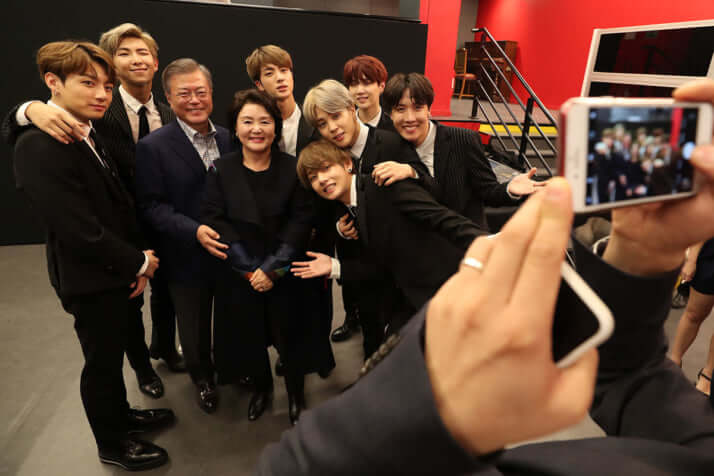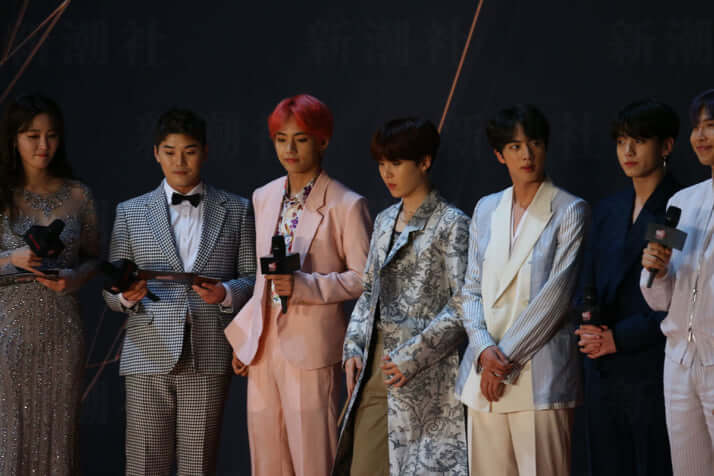ハグ会でアイドルに無理やりキスも 「推し活」は本当にポジティブなものなのか… 相次ぐ「暴走ファン」による事件
暴力沙汰に発展した「≠ME」イベント 今や「出演者」となったファンたち
4月末に発生した、「≠ME(ノットイコールミー)」のシングル発売記念イベントでの警察沙汰も記憶に新しい。「優先入場券」が当たらなかったファンの一部が押し寄せ、スタッフを負傷させたという一件はネットニュースでも取り上げられた。
ファン同士の小競り合いが、なぜそこまでエスカレートしたのか。根底には「自分の推しをもっと近くで見たい」「接触を邪魔されたくない」という強い独占欲がある。応援という名目で他者や運営を敵視し、物理的な行動に出るというゆがんだ心理状態は、「推し」という存在が自身の行為を正当化する危うさを示している。
報道によれば事前に「もしかしたら伝説の乱闘があるかも」という書き込みを見たという証言もあり、もともとステージの中止をたくらむ「壊し屋」行為だったのではという指摘も出ている。
演者と観客の間には本来、舞台は尊重すべきもの、という共通の認識がある。しかしSNS時代の今、自分自身と推しとの距離が縮まったと感じる人は多くなり、「観ている自分」もコンテンツの一部だという意識が強くなっているのだろう。
最近ではお笑い芸人のトークライブ中や、観劇中に平然と私語を続ける観客の存在が報じられ、自己表現とマナーの境界が曖昧になっていることがうかがえる。推しだけのステージではなく、自分も目立つためのステージであり、「自分が楽しければそれでいい」という観客の姿勢は、昔の見る側の作法とは大きく異なる。
演者との距離が近づいたと感じることは、昔からファンにとって喜びであり魅力の一つだ。だがその「近さ」を履き違えたとき、観客は推しの表現を阻害する存在となる。
客席が騒がし過ぎては、推しにスポットライトが当たらない。同じファン同士でも、「それは違う」「その行為は推しのためにならない」とブレーキをかける風土を育てることが必要なのと同時に、過剰な「推し行為」を正当化しないことも求められているのだろう。1億総「推し活」時代における、「引く」ことの大切さを見直す局面に来ているのではないだろうか。