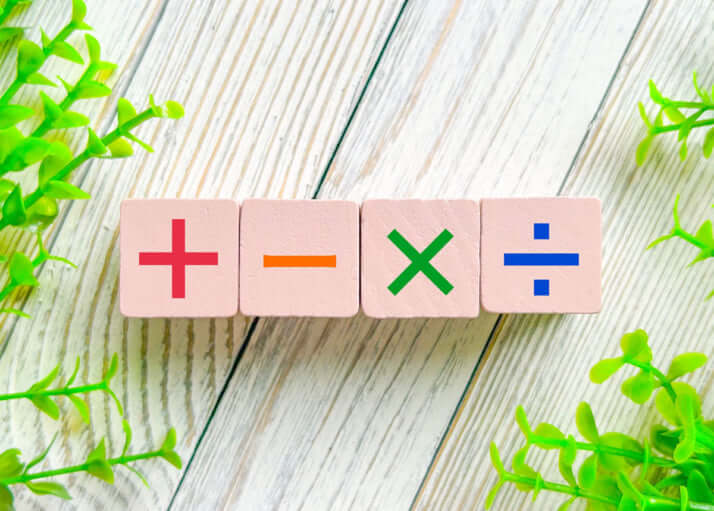大学で「足し算」「かけ算」を教える意味はあるのか? 実際に教えた数学者が「ある」と胸を張るワケ
大学で「義務教育レベル」の内容を教える――そんな授業が、財務省の審議会で問題視された。東京理科大学理学部教授や桜美林大学リベラルアーツ学群教授を歴任し、数学教育に半世紀以上携わってきた芳沢光雄氏は、実際にそんな授業を行ってきたひとりだ。大学で足し算やかけ算の四則計算を改めて学ぶ大学生たちを、芳沢氏は「教育の犠牲者」だと語る。
***
【実際の回答を再現】厳しすぎ?意地悪?漢字テストで”不正解”になった「男」「加」「口」
4月15日に財務省で開催された財政制度分科会の内容が、波紋を呼んでいる。翌日の朝日新聞朝刊に掲載された記事「一部私大の授業『義務教育のようだ』財務省『助成見直しを』」によると、基礎的な内容を大学の授業で教えることを、財務省が問題視したものである。数学に関していえば「四則演算や方程式の取り扱い」といった点がそれにあたる。
その先には私学助成についての議論があり、この点に関しては様々な意見がある。だが、多くの識者に「極めて易しい内容であるにもかかわらず、あえて大学の授業で扱わざるを得ない、高校までに学ばなかった低学力の学生がいる」という共通意識はあるようだ。
本稿では、筆者の実践などを鑑みて「低学力の学生に、大学でわざわざ教える必要がない」という意識に異論を呈したい。
筆者の授業も「批判の対象」に
筆者は、一昨年の3月に大学教員人生45年に幕を閉じるまで、10の大学に専任・非常勤として勤務し、合わせて約1万5000人を対象として、数学の授業を担当してきた(文系理系半々)。また、それらとは別に1990年代後半から、全国各地の小中高校で合わせて約1万5000人に、算数・数学に対する興味・関心を高める目的をもって「出前授業」を行ってきた。
財政制度分科会の資料によると、やり玉に挙がった数学に関する内容は「四則計算」「割合%」「約数と倍数」「方程式と不等式」の4つである。最後の本務校、桜美林大学リベラルアーツ学群では、専門の数学、教職の数学、ゼミナール、リベラルアーツの基礎、などのほかに「数の基礎理解」という授業を定年まで行い、そこでは先の4つについても堂々と講義を行った。
その授業の内容は、拙著『昔は解けたのに……大人のための算数力講義』(講談社+α新書)に収められているが、一言で述べると「算数+α」の内容である。最近、筆者が行ったこの授業についても「財務省の批判の対象ではないか」という問い合わせが相次いでいる。
[1/4ページ]