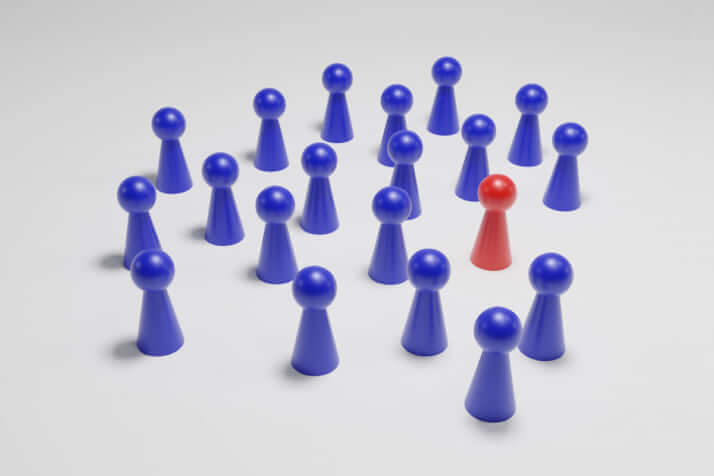「東大出身のマスター」が出すお酒はウマいのか――日本にまん延する「学歴信仰」の謎
近年、価値観の多様性が謳われる一方で、なぜか学歴偏重主義だけはますます強まっているようだ。アイドルやお笑い芸人など、かつては学歴とは無関係と思われていた職業も、今では出身大学などが取り沙汰されることが普通になっている。
速報“契約ゼロなら最低賃金に” 「やさぐれ営業マン100人」で31億円詐取「プルデンシャル生命」の特殊事情
速報「“心ここにあらず”といったご様子」 関係者が案じる、秋篠宮さまの“異変” 「随分とおやつれになった」
速報「中道」結成に高市首相は「焦りを隠せず」 学会員に出された秘密指令で「萩生田氏には最悪の展開が」
夜の世界も例外ではない。「以前、バーのマスター(店主)が東大出身だということで評判になったお店がありました」――そう指摘するのは甲南大学教授の尾原宏之さん。以下、尾原さんの新刊『「反・東大」の思想史』(新潮選書)から一部を再編集して、日本社会にまん延する奇妙な「東大信仰」の一端を紹介する。
***
最後に残された「偏見」
日本近現代史上、ここまであからさまに「低学歴」への侮蔑と「高学歴」への賞賛が語られる時代は、実は現在がはじめてではないだろうか。ネット上の各種の論争でも、他人の学歴に対する揶揄(たとえば「ネトウヨ」に対して)はごくごく当たり前である。ユーチューバーたちは大学ランクや偏差値に関する話題、超難関大学に合格した秀才エピソードを毎日のように面白おかしく提供してくれている。
人々の本音がむき出しになるインターネット界隈だけではなく、表向きは学歴差別を批判するリベラルなメディアも、難関中高合格や国立大医学部合格、アイビー・リーグ留学、お受験ママの奮闘などについては賞賛と奨励を惜しまない。学歴に関することをおおっぴらに話すのは浅ましいことだ、というかつては多少あったはずの良識めいたものも、消滅してしまったかのように見える。
米国の政治哲学者マイケル・サンデルは、ベストセラー『実力も運のうち 能力主義は正義か?』の中で、「人種差別や性差別が嫌われている(廃絶されないまでも不信を抱かれている)時代にあって、学歴偏重主義は容認されている最後の偏見なのだ」と語った。
日本でも女性差別やマイノリティ差別は、かつてに比べればはばかられるものになっている。だが、入学難易度の低い大学の出身者や、そもそも大学に進学できなかった人々への揶揄、その反面の難関大学合格者に対する賞賛は、社会のいたるところで目につくようになった。
サンデルも指摘するように、生まれつきの属性は個人の努力ではどうにもならないが、受験の結果は本人の努力や怠慢の結果、つまり自己責任だと一般的に考えられているから、差別する側の心理的ハードルは低い。もちろん日本においても現実は単純ではなく、子供の進路が家庭環境や親の学歴に大きく依存することは、これまで教育社会学の研究が明らかにしてきたことである。
「東大出」の酒の味
サンデルが同書で紹介した研究が示すように、「低学歴」に対する低評価、「高学歴」に対する高評価は、学歴を持たない人々でさえ内面化しがちである。日本でも、自身の学歴に対する卑下や、難関大学出身者に対する過剰な敬意などが随所で観察できる。
筆者の見聞でも次のようなことがある。筆者は、数年前まである都市に存在したバーに足繁く通っていた。そのバーの店主は俗に日本一と呼ばれる中学・高校から東京大学法学部に進み、大企業で課長まで昇進するも、退社したのちに夜の店の経営を始めた。
不思議だったのは、夜の街の同業者や客の多くがこの店について語る時、店そのものの良し悪しよりも「○校出身」「東大出」という点を必ずといっていいほど強調、連呼したことである。灘や開成、東大の出身だと酒の味がよくなるなら別だが、脱サラして苦闘する店主に対してやや失礼ではないか、とも思われた。
だが、よくよく見ると店主自身も東大を売りにしている気配がある。高学歴とは無縁な同業者や客からすれば、東大出の店主の仕事ぶりにあれこれ文句をつけ、からかえるところにこそ妙味があったのかもしれない。いずれにせよ、大学と縁のない人でも東大には非常に大きな価値を感じている様子がよくわかった。
「東大は日本そのもの」?
多くのエリート校が存在する米国とは異なり、日本の場合、サンデルのいう「学歴偏重主義」の頂点には常に東大が君臨し、人々のマインドを支配している。それは、日本の近現代そのものが東大を頂点とするシステムによって生み出されたことと関係するだろう。ある研究会で、京都大学出身の社会学者が「要するに東大が日本そのものなんですよ」と語るのを聞いたことがある。これはいい得て妙のフレーズである。
歴史をさかのぼると、国家が作った大学である東大とその前身校の使命とは、つまるところ日本の近代化を急速に推し進める人材を急速生産することにあった。つい最近までマゲを結っていた人々とその子息の中からエリートを急造し、民衆を統治させ、各方面の指導にあたらせる。
明治維新から最初の対外戦争である日清戦争まで26年、日露戦争まで36年しか経っていない。短期間で巨大な機構を作り上げ、各方面に指導者を配置しようとするのだから、随所で大きな無理や摩擦が生じた。その無理や摩擦の吸収と克服を積み重ねて、現代にいたる日本が形成されていく。
***
甲南大学の尾原教授は次のように指摘している。
「歴史的に東京大学は最高学府の頂点に君臨してきました。しかし一方で、東大がそのような特権的な地位を占め続けることに反発する教育者・思想家が数多く存在したために、東大の一極集中が多少なりとも緩和され、社会の多様性が保たれてきた側面があります」
「この世の中には、偏差値だけでは測れない価値がたくさんあります。もし現在の“東大信仰”が行き過ぎているとすれば、誰かがそれに対抗する価値観を打ち出す必要があると思います」
※本記事は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)に基づいて作成したものです。