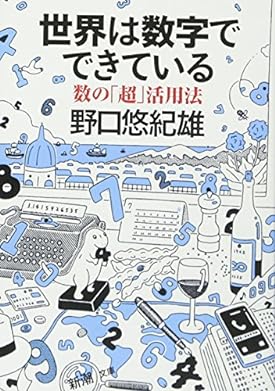ラッキー7、七味唐辛子、世界の7不思議、虹の色、週7日……人はなぜ「7」が好きなのか
1週間がもっと短くて、働く日数も少なければ良いのに……。月曜から金曜まで休みなく働くなんて不条理だ……。ましてやこんな暑い季節、ただじーっとしているだけでも熱中症になりそうなのに、なんで1週間はこんなに長いんだ……。なんて思いながら、毎朝満員電車で汗水垂らして働いているサラリーマンの方も多いはず。
速報中国人観光客の減少に「ずっとこのままでいい」 京都では喜びの声が 一方、白川郷では「墓に登ったり、私有地で用を足したり…」 地元住民は嘆息
速報「月給20万円のほとんどを詐欺につぎ込み…」 ロマンス詐欺を巡って逮捕の僧侶は「詐欺被害の常連」だった だまされ続けた“複雑な事情”とは
速報じわじわ進む「高市離れ」とあなどれない「創価学会票」で……「30弱の選挙区で自民が中道にひっくり返される」衝撃予測
しかし1週間7日間という暦は、古代バビロニアで誕生し、紀元前1世紀頃のギリシャ・エジプトで完成したと考えられており、私たち平成の世に生きる人間が騒いだところで、どうにかなるような問題でもないようだ。
実は、フランスではフランス革命後1カ月を10日ずつに3分割する「デカード」という暦を採用したり、ソビエト連邦では5日からなる週を採用したりと、かつて世界では1週間=7日ではない暦を使用したケースもある。しかしいずれも不評だったため長続きせず廃止されている。
ではなぜ7日なのか。経済学者の野口悠紀雄氏は著書『世界は数字でできている―数の「超」活用法―』の中で、実は7という数字はマジカルナンバーなのだと述べ、その理由は人間の記憶力にあると解いている。(以下同書より抜粋、引用)
***
1カ月を構成する日数は、一度には把握しにくい。そこで、週を単位にして把握する。問題は、1週を何日にするかだ。フランス革命暦やソ連革命暦の失敗は5日では少なく、10日では多いことを示した。
アメリカの心理学者ジョージ・ミラーは、人間の短期記憶の容量が7±2(人によって差がある)であるとする論文を1956年に発表した。
「7以上になると区別がつきにくくなる」とは、日常経験でも明らかだ。虹の色は7色であり、1オクターブには7個の音があると把握している。「世界の7不思議」や「7つの大罪」も7だ。軍や企業などの多くの組織は、7名や7部署をひとくくりにしたピラミッド構造を作る。新約聖書の「ヨハネ黙示録」は、7のオンパレードだ。日本では、七福神、七草、七味唐辛子など。
「7あたりが限度」という法則は、日常生活に応用することもできる。例えば、引き出しは7個くらいまでにしたほうがよい。それ以上になると、どこに何を入れたかがわからなくなる。
逆手に取ることも可能だ。例えば、面接試験で「愛読書は何か?」と聞かれたら、7点以上挙げて目くらましを狙う。面接官は幻惑されて、「何という読書家だろう!」と評価してくれるかもしれない。
***
1週間は長いなあ……と思っているあなたも、マジカルナンバー「7」を受け入れ、逆に巧みに使うことによりスマートに生き抜こう!