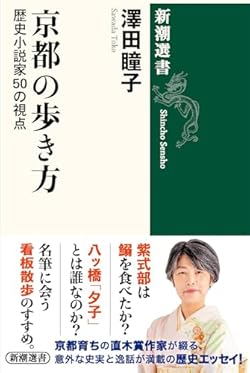「酒を飲めるやつは出世する!?」 NOと言いにくい日本特有の「組織単位飲み」のルーツは1300年前にあった
体質的にお酒が飲めないのに、「飲み続ければ飲めるようになる」「まあ乾杯だけ」と、あの手この手で飲ませようとしてくる手合いに悩まされている人も多いだろう。
速報「1日の儲けは2000万円」 東京・御徒町に中国人“金密輸グループ”の拠点があった! 現地を訪れると、怪しげな男たちの姿が…
速報聴衆3000人「勝つぞ」コールが響き渡る「高市フィーバー」で自民大勝? 一方、石破前首相への応援演説依頼が相次いでキャンセル
速報「秋篠宮家に騙されたようなモノ」 紀子さまの実弟に絡んだ“1億円金銭トラブル”が発覚! 「皇室と聞くだけで絶大な信頼をしてしまった」
作家の澤田瞳子さんもその一人。最近遭遇したある宴席での出来事から、なぜ日本では組織単位で酒を飲む伝統があるのかを歴史的に考察しつづっている。澤田さんのエッセイ集『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』から、その一篇をご紹介する。
***
体質的に酒が飲めないと公言して、かれこれ20年。はじめのうちは、「いや、頑張れば飲めるようになるって」「一杯ぐらい大丈夫でしょ」と強いられることも多かった。しかし世の中も少しずつ変化し、アルコールハラスメント、通称・アルハラとの言葉も一般化した令和のご時世、嫌な思いをする機会ももはや過去の話――と思っていた矢先のことだ。
「いや、それは飲まないと」
と、先日、久しぶりに無理やりワイングラスを目の前に置かれた。
異業種の方々とご一緒したある宴席。わたしの隣にいらした男性が、彼には目上に当たる別の方が勧めて来られたワインを断ったわたしを、「~~さんが勧めているんだからいただかないと!」と制したのだ。
なるほど。世間には、自分が人にへつらう手段として他人に酒を飲ませるケースもあるのか。腹が立つよりも、感心した。もっとも飲めないものはどうしたって飲めないので、注がれたワインは右から左に置き直しただけで、その後は手も触れなかったのだけど。
政治や儀式の一部だった「飲酒」
忘年会や新年会、はたまた歓送迎会など、日本では組織単位で酒を飲む機会が多い。アルハラという概念が生まれ、それが悪しきものと見なされるに至ったのはそんな背景によるのだろうが、そもそもこの国では古くより飲酒と組織は不可分だった。なぜなら奈良時代や平安時代の貴族社会で、飲酒――というか宴会は、政治や儀式の一部だったためだ。
一例として、毎年元日の天皇や貴族の動きを見てみよう。天皇はまず大極殿(だいごくでん)で、貴族たちから正月の祝賀を受ける。その後、座を移して、今度は天皇が主催する宴が開かれる。途中で音楽が奏でられたり、参加した貴族たちに天皇から賜りものがあったりするが、これは決して今日の我々が考える新年会ではない。天皇と臣下が酒食を共にするという、れっきとした「儀式」なのだ。
こういった天皇が貴族を集めて行う公式な宴会を、節会(せちえ)と呼ぶ。正月なら元日、7日、16日。この他、3月3日、5月5日、7月7日といった節目の日や、外国の使節が来たり、反対に唐国に渡る遣唐使が任命されたりしたときにも開かれる。仕事で酒が飲めるのを嬉しいと取るか、面倒と取るか。それは人によって異なるだろうが、上司部下との酒の飲み方が現代以上に地位や出世に関わっていたことは間違いがない。わたしのような下戸は、相当苦労させられただろう。
酒に命を救われた光仁天皇
しかもこの節会にはしばしば、穏座(おんのざ)という二次会も設けられていた。いや、節会は儀式なのだから、当時の人々の認識としては穏座こそが我々の思う「宴会」とするのが正しい。ただいずれにしても、彼らはそこでも引き続き酒を飲んでいたわけなので、貴族社会と酒は切り離せないものだったわけだ。
一方、こういった仕事としての飲酒の他、個々人で酒を嗜む者も、当然存在した。そんな人々の中で興味深いのが、京都もとい平安京に都を定めた桓武天皇の父親・光仁天皇の酒の飲み方だ。
数え年62歳、当時にしては高齢で天皇の座についた彼は、もともとの名前を白壁王(しらかべおう)といい、大化の改新(乙巳〈いっし〉の変)を断行した天智天皇の孫。ただ少年時代に父親を亡くしたこともあって出世は遅く、世間的には半ば忘れ去られた不遇な皇族だった。
彼が青年・壮年期を過ごした奈良時代末期は、藤原氏が権力を握りつつある時代だった。21歳の時には、当時左大臣として政治を取っていた長屋王が、49歳の時には、前左大臣の息子・橘奈良麻呂と長屋王の皇子たちが、政(まつりごと)を覆(くつがえ)さんとしたと疑われて死に追い込まれる。そんな危険極まりない状況の中で、どうにか生き残る術を模索した白壁王は、「酒を縦(ほしいまま)にして迩(あと)を晦(くら)まし、故をもって害を免じる」、つまり酒に溺れるふりをして世間の目をあざむき、難を逃れたと『続日本紀(しょくにほんぎ)』に記されている。縦という言葉からは、自宅でも連日浴びるように飲み続け、その噂が世間に流れるままにしたのではと推測される。
月日は流れ、怪僧とも呼ばれる道鏡を寵愛した女帝・称徳天皇が亡くなる頃には、男性の皇族は相次ぐ政変のせいで激減していた。かくして齢(よわい)60を超えた古皇子・白壁王は見事に身を守り通し、光仁天皇として即位する。つまりこれは、酒に命を救われた例と言えよう。
美しい姫「酒人内親王」
ちなみに光仁天皇の子の一人に、酒人(さかひと)内親王という姫がいる。自分の身を救った酒に感謝した父親が、娘にこんな名をつけたわけではない。当時の皇族は、養育を担当した氏族の姓を名とするケースが多い。この内親王の場合、酒人連(さかひとのむらじ)氏という氏族が彼女を育てたことが名の由来だろう。もっとも酒人連氏は古くは神酒の醸造に関わった氏族なので、酒と完全に無縁というわけではない。
酒人内親王は異母兄・桓武天皇の妃となり、76歳で亡くなる。その死を記す『日本後記』逸文には「容貌殊麗(しゅれい)、柔質窈窕(ようちょう)」と彼女が美しい女性だったと記されている。では気性はといえば、記録は「為性倨傲(ひととなりきょごう)にして、情操修まらず」と続く。倨傲とは傲慢に近い意味なので、美人だが傲慢かつ気まぐれな女性だったわけだ。ただ17歳年上の桓武天皇は、そんな酒人内親王を好きにさせていたというから、よほどの魅力にあふれた女性だったのだろう。
一方で彼女は肉親との縁が薄く、実母・井上内親王は光仁の次の天皇位を巡る政変に巻き込まれて怪死。夫の桓武はもとより、朝原内親王という一人娘にも先立たれる。彼女が晩年に記した遺言書には、葬儀は簡略にして、財産のしかるべき分は長年仕えてくれた者たちで分けよと記されているので、高飛車な一方でサバサバしたところもあった様子だ。だとすれば長きにわたるその暮らしの中で、彼女もまた酒を――しかもわたしが遭ったような誰かにへつらうための酒ではなく、純粋に自らのためだけに酒を楽しむ折も多かったかもしれない。
※本記事は、澤田瞳子『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』(新潮選書)を再編集したものです。