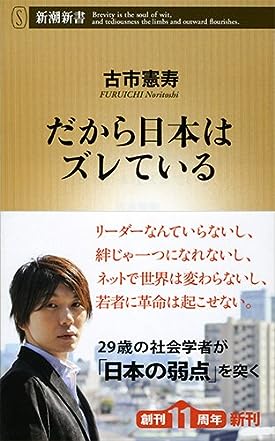なぜ新入社員は毎年「期待ハズれ」なのか――古市憲寿氏が読み解く
「今年の新人は使えねー」「うちの新人、こんなことも知らなかったんだよ」
この手のグチ、陰口は4月のこの時期に社内で必ず聞えてくる。「新人使えない話」は会社では鉄板のネタだ。
たしかに新人は「無知」で「使えない」ことが多いのだろう。でも、そうグチっている人だって、ほんの数年前までは「無知」で「使えない」新人だったんじゃないのか。若手社会学者の古市憲寿氏は、新著『だから日本はズレている』(新潮新書)の中で、「そもそも新社会人がすぐに使えるはずがない」と述べている。社内での恒例行事となっているこの不毛な光景をどう考えればいいのか。同書から引用してみよう。(同書内、「新社会人の悪口を言うな」より)
「入社式」というイニシエーション・セレモニー
――新社会人の皆さん、おめでとうございます。これから社会という荒海にこぎ出す皆さんに、今日は伝えておきたいことが二つあります。一つは、社会において信頼がいかに大切か、ということ。そして、内向きになるな、グローバルに活躍して欲しいということです。先輩社員の目を気にすることなく、皆さんにはフレッシュな感性を思う存分活かして欲しいと思います。がはは……――
みたいな社長挨拶に代表される、つまらない新入社員向けのメッセージを毎年耳にする。若者は就活に勝ち抜くと、「入社式」を経て、「社会人」となる。4月1日のニュースで報じられる入社式の風景は、もはや春の風物詩である。
しかし、このように桜の季節に大規模な入社式が行われ、それがメディアで大々的に伝えられるようになったのはせいぜい1970年前後のことである。
大規模な入社式というのは、新卒一括採用というシステムなしには成立し得ない。自営業者が多くて、大企業もそこまでなかった時代の日本では入社式がニュースになることは滅多になかった。
大規模な入社式を催すというのは日本独自の慣習だ。新卒一括採用のない海外では、会社の入社時期はみんなバラバラである。だから入社式もないし、それは春の風物詩でもない。つまり、春になるたびに毎年「新入社員諸君」と、一斉に大人たちが偉そうになれるのは、ほぼ日本独自の風習といっていいだろう。
入社式は英語に翻訳しにくい言葉だ。無理やり訳すと「initiation ceremony(イニシエーション・セレモニー)」になる。イニシエーション、つまり特定のクラブや集団に加入するための儀式ということだ。カトリックの洗礼や、フリーメイソンへの入会儀式も一種のイニシエーション・セレモニーである。
つまり、フリーメイソンよろしく、会社という一つの特殊なコミュニティに参入してくる新参者たちに、先輩たちがその集団のルールを説くのが入社式という場である。そう言われてみると、入社式とは確かに宗教っぽい儀式だ。
しかし入社式でその会社独自のルールが説かれることは少ない。むしろ、「採用基準」と同様に、どこの会社も似たり寄ったりなことばかりを言う。信頼、社会的使命、独創性、グローバルマインド、チャレンジ精神など、いくつかの言葉を組み合わせれば誰でも新入社員向けメッセージが作れてしまう。
■革新性のない社長挨拶
その新入社員向けのメッセージというのは、この数十年間あまり進化を見せていない。
今から約40年前、1971年4月1日の『読売新聞』は当時の入社式を次のように報じている。日産社長は訓示で「組織に飼い慣らされずに、逆に活力を吹き込む人間を期待する」と若者に呼びかけた。東芝社長は「消極的な気持ちではいけない。自分の創造力を生かす心づもりではいってほしい」。トヨタ社長は「国際的感覚を身につけ広い視野にたって仕事をしてほしい」。
翌年の『読売新聞』も新入社員向け社長訓示を採録しているが、どこの企業も似たり寄ったりな内容だった。当時「日本一のマンモス企業」だった新日本製鉄社長は「幸福も繁栄も、他人から与えられるものではない」。帝人社長は「まず自分に勝つこと。それには独創的な見識を持つことが望ましい」。三菱金属鉱業は「社会、会社を動かすのは若いエネルギーだと信じている」。
時代は飛んで2012年、新日本製鉄社長の新入社員向けメッセージを読んでみると「自らを鍛え、磨くという気持ち」「グローバルな情報への感度」が必要だとしながら、「皆さんの持つ若い力と瑞々しい感性を、思う存分発揮してもらう」なんてことが書いてあった。
どうやら社長訓示というのは、基本的に会社名と年次を入れ替えても成立するようなものばかりらしい。
別にここで大企業の新入社員向けメッセージの空虚さを批判したいわけではない。というか、それは空虚で大いに結構なのである。なぜならば入社式というのは儀式であって、形式にこそ意味があるからだ。社長が新入社員に向けてメッセージを発するという儀礼自体が重要なのであって、内容はどうでもいいといえばどうでもいい。
面白いのは、空虚な訓示を発する入社式なるものを、未だに多くの企業が同じ4月1日に実施し続けているという点である。新入社員に向けては散々、チャレンジ精神の発揮を呼びかけているにもかかわらず、独創性の欠片(かけら)もない。
■「社会人」は日本にしかいない
入社式を迎えた人々は普通「新社会人」と呼ばれる。しかし「社会人」という言葉は、「入社式」同様に不思議な概念である。
人は、入社式を迎えると急に「社会人」になる。ということは、子どもや学生は「社会」に生きていないということなのだろうか。もしくは入社式を経験しないフリーターや日雇い労働者たちは「社会人」ではない、ということなのだろうか。
「入社式」同様、「社会人」を英語に翻訳するのは難しい。「成人」や「大人」なら「adult (アダルト)」でいいが、微妙にニュアンスが違う。あえて訳すなら「full member of society (社会の正規メンバー)」となる。
「社会人」も「入社式」同様、日本に独特な概念である。しかもこの二つが結びついてしまったところに日本の特殊性がある。
入社式という儀式を経て会社員になることが、「社会人」であることと同義になる。翻って、入社式が準備されないようなフリーターたちは「社会人」ではないと見なされ、社会保障など待遇の面でも「社会人」とは差を付けられる。
まさに入社式という儀式が、「社会」に入れるか入れないかの通過儀礼としての機能を果たしてしまっているのである。
ではその「社会人」というのは、どれほど素晴らしい人々なのだろうか。
就活生たちにとって、有名企業で働く人々は神様のように見えるという。何百倍という倍率を勝ち抜いて、誰もが憧れる企業で「社会人」になれた人たちだ。さぞ仕事もできて、かつプライベートも充実している、きっと完璧な人間なのだろう、というわけだ。
確かに企業の採用ページに載っている先輩社員紹介などを見てみると、「社会人」というのはさも立派な人なのだろうなという気がしてくる。
僕の友人が働いていた大手広告代理店の先輩紹介ページでは、「毎日ワクワクした仕事の連続」「カフェでよくアイディアが思い浮かぶ」「夢は人々がハッピーになること」といった言葉が並び、本当にそこが素敵な仕事場に思えてくる。
連日のように27時過ぎまでメイクの落ちきった顔で働き、肉体も精神もボロボロ、唯一の癒しは韓流アイドルの曲を聴くことという友人にもこのサイトを見せてあげたい。
やはり僕の友達が働く出版社の「先輩」たちも、ものすごく楽しそうだ。「プレッシャーこそありますが、めっちゃ醍醐味に満ちた仕事」「悪戦苦闘しているうちに会心のアイディアが見つかったりしたときにはもう、快哉を叫びたくなります」と、毎日の仕事が興奮の連続だろうということがわかる。
週刊誌に配属されて、「事件とかもう見たくない」「先輩に風俗に誘われるような文化がもうイヤだ」「バレンタインの夜に会社へ呼び戻されて今度こそ限界」とか言っている友人にもこのサイトを見せてあげたい。
[1/2ページ]